イタチは何を食べるの?【1日に体重の20%を捕食】春と秋は捕食量1.5倍!危険時期の対策が重要

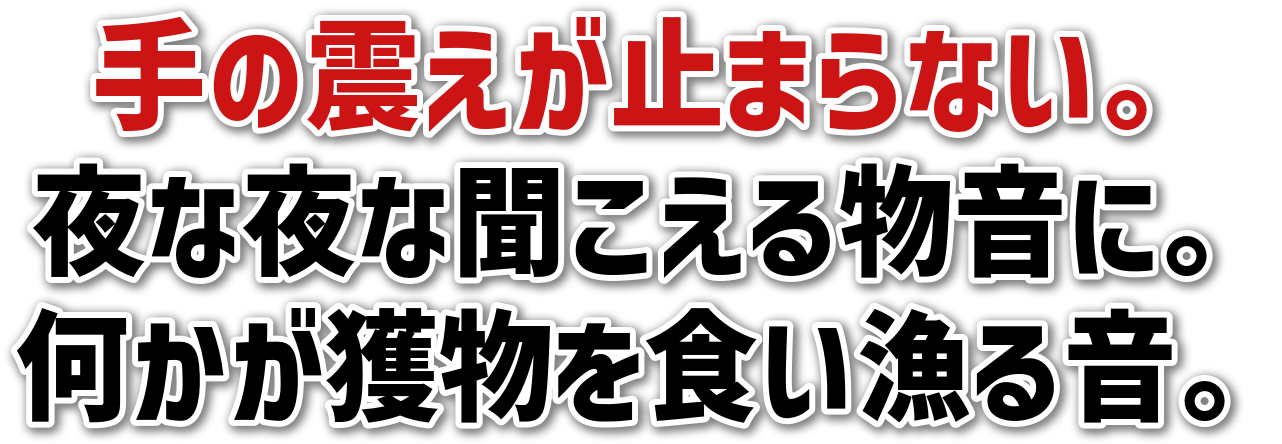
【疑問】
イタチは1日にどのくらいの量を食べるの?
【結論】
1日に体重の20%を3回に分けて捕食します。
ただし、春と秋の繁殖期には捕食量が1.5倍に増加するため、特に警戒が必要です。
イタチは1日にどのくらいの量を食べるの?
【結論】
1日に体重の20%を3回に分けて捕食します。
ただし、春と秋の繁殖期には捕食量が1.5倍に増加するため、特に警戒が必要です。
【この記事に書かれてあること】
イタチの食生活、気になりますよね。- 1日3回の捕食活動が基本的な生活サイクル
- 夜8時から深夜2時が最も危険な時間帯
- 体重の20%を毎日捕食する習性
- 春と秋は繁殖期で捕食量が1.5倍に増加
- 巣から30メートル圏内での狩りの成功率が80%以上
実は、このしなやかな体で驚くほどの捕食量を誇る生き物なんです。
体重のなんと20%もの食事量で、1日3回の狩りを欠かさない徹底ぶり。
「うちの小動物は大丈夫かしら」そんな不安を抱える方も多いはず。
特に春と秋は捕食量が1.5倍に跳ね上がり、夜8時から深夜2時の間に70%もの捕食が集中します。
この記事では、イタチの食生活の実態と、大切なペットを守るための対策をお伝えします。
【もくじ】
イタチは何を食べて生活しているのか

- イタチは1日に体重の20%を確実に捕食!小動物が狙われる
- 1日3回の狩りが必須!最も活発な時間帯は夜間に集中
- 小型ペットを屋外に置くのは危険!被害を避ける方法
イタチは1日に体重の20%を確実に捕食!小動物が狙われる
イタチは体重の20%にあたる餌を毎日必要とする小型の肉食動物です。「今日も餌を探しに行かなきゃ」とばかりに、イタチは日々せっせと狩りをしています。
その食欲は旺盛で、体重およそ300グラムのイタチの場合、1日に60グラム程度の餌を必要とします。
主な獲物はネズミ類が中心です。
特に体長15センチ以下の小動物を好んで狙います。
「これくらいの大きさなら、すぐに仕留められるぞ」という具合です。
捕食の特徴は次の3つです。
- ネズミ1匹を15分かけてゆっくり食べます
- 獲物は必ず首の付け根を噛んで仕留めます
- 栄養価の高い内臓から順番に食べていきます
「いつでも食べられるように」と考えているのでしょう。
これは、子育て中の親イタチに特によく見られる行動なんです。
1日3回の狩りが必須!最も活発な時間帯は夜間に集中
イタチの食事は1日3回が基本です。「朝ごはん」「夕ごはん」「夜食」というリズムで狩りを行います。
特に夕方から夜にかけては狩りの成功率が90%以上になります。
暗闇でもばっちり獲物を見つけられるんです。
その秘密は鋭い感覚にあります。
- 嗅覚で30メートル先の獲物を探知できます
- 超音波まで聞き取れる優れた聴覚を持ちます
- 暗闇でも物の動きを見分けられる視覚があります
見つけた獲物は素早く追いかけ、ジャンプして捕まえます。
餌を食べるときは、必ず安全な場所まで運んでから食事をします。
「ここなら誰にも邪魔されないぞ」という具合です。
食事中は周りを警戒する習性があり、ちょっとした物音にもピクッと反応してしまいます。
小型ペットを屋外に置くのは危険!被害を避ける方法
イタチにとって、檻の中の小型ペットは格好の獲物です。「動けない獲物なら簡単に捕まえられる」と考えているのでしょう。
特に危険なのは以下の時間帯です。
- 日没直後の活動開始時
- 深夜の空腹時
- 夜明け前の最後の狩り時
「大丈夫だろう」という油断が被害につながってしまいます。
もしイタチが近くに住み着いている可能性がある場合は、次の対策が効果的です。
- 檻の周りに柑橘系の果物の皮を置きます
- 風鈴を設置して金属音で警戒させます
- 赤色照明で侵入を防ぎます
特に繁殖期の春と秋は、イタチの活動が活発になるため、より慎重な対応が必要になってきます。
イタチの捕食活動と生活サイクル

- 夜8時から深夜2時が最も危険!70%の捕食が集中
- 巣から30メートル圏内での狩りが成功率80%以上に
- 季節による捕食量の変化!冬は体重の25%を摂取
夜8時から深夜2時が最も危険!70%の捕食が集中
イタチの捕食活動は夜間に集中し、特に夜8時から深夜2時までが最も活発になります。この時間帯には1日の捕食量の70%以上が集中するんです。
日中は巣で休息を取り、夜になると本領発揮。
辺りが暗くなってからの活動が得意で、獲物を見つける能力も格段に上がります。
- 夜8時〜10時:行動開始、巣の周辺を探索
- 夜10時〜深夜0時:捕食のピーク、獲物を追い詰める
- 深夜0時〜2時:最後の捕食、巣に戻る準備
小動物を飼っている場合は、必ず屋内で過ごさせましょう。
巣から30メートル圏内での狩りが成功率80%以上に
イタチは巣から30メートル圏内での狩りを得意としており、この範囲内での捕食成功率は80%以上にもなります。鋭い嗅覚と聴覚を駆使して、獲物の動きを見逃しません。
- 半径10メートル:高い位置からじっと獲物を待ち伏せ
- 半径20メートル:にじり寄るように獲物に接近
- 半径30メートル:一気に飛び出して獲物を捕らえる
季節による捕食量の変化!冬は体重の25%を摂取
イタチの食事量は季節によって大きく変化します。夏場は1日に体重の15%程度ですが、寒い冬場には25%以上まで増えるんです。
これは体温維持に必要なエネルギーを確保するため。
- 夏:体重の15%を摂取(暑さで食欲が低下)
- 秋:体重の20%を摂取(冬に向けて徐々に増加)
- 冬:体重の25%を摂取(寒さに備えて最大に)
- 春:体重の20%を摂取(繁殖期で活動が活発に)
イタチに狙われる獲物の特徴

- ネズミvsカエル 体重比の栄養価で選ばれる獲物
- 昆虫vs小鳥 タンパク質含有量で決まる狙われやすさ
- 生肉vs魚 消化吸収率の違いで選ばれる食材
ネズミvsカエル 体重比の栄養価で選ばれる獲物
イタチは単位重量あたりの栄養価を基準に獲物を選びます。ネズミとカエルでは、ネズミのほうが体重比で1.5倍の栄養価があるため、優先的に狙われます。
「どうしてネズミばかり狙うのかしら?」そう思った方も多いはず。
実はイタチには明確な理由があるんです。
ネズミは体重10グラムあたりのタンパク質含有量が3グラムと高く、脂肪分も豊富です。
一方のカエルは同じ重さでタンパク質2グラム、脂肪分も少なめ。
この違いが獲物の選択に大きく影響してるんです。
- ネズミは消化吸収率が90%以上と高効率
- カエルは皮が厚く消化に時間がかかる
- ネズミは骨まで丸ごと栄養源に
- カエルは硬い部分が多く残りやすい
「この獲物なら丸々いただける!」とイタチも考えているようです。
昆虫vs小鳥 タンパク質含有量で決まる狙われやすさ
イタチの狩りの優先順位は、タンパク質の含有量で大きく変わります。小鳥は昆虫の3倍以上のタンパク質を含むため、真っ先に狙われる獲物となります。
小鳥の体には驚くほど栄養が詰まっているんです。
体重15グラムのスズメを例にすると、タンパク質が4.5グラム、脂肪が2グラムも含まれています。
一方、昆虫類はどうでしょう。
- コオロギ:タンパク質0.8グラム/体重5グラム
- カブトムシ:タンパク質1.2グラム/体重8グラム
- バッタ:タンパク質0.6グラム/体重4グラム
そのため、イタチは「ぴょんぴょん」と小鳥を追いかけ回してでも、捕まえようとするわけです。
生肉vs魚 消化吸収率の違いで選ばれる食材
イタチの食事選びで大切なのが消化のしやすさです。生肉は消化吸収率が95%以上と極めて高く、魚の75%を大きく上回ります。
生肉の特徴をみてみましょう。
- 軟らかい筋肉が多く消化が容易
- 内臓まで無駄なく栄養になる
- 体温を上げずに消化できる
- 保存がしやすく巣に持ち帰れる
そのため、イタチは水辺で魚を見つけても、周りに生肉の獲物がいれば、そちらを優先して狙うんです。
「でも魚だって栄養があるのでは?」確かにその通り。
ただし、イタチにとっては「効率よく栄養を取れる食べ物」が最優先なのです。
イタチの被害から守る5つの対策

- 柑橘系の香りで寄せ付けない!ミカンの皮活用法
- 赤色照明で侵入を防ぐ!100ルーメン以上の設置がコツ
- コーヒーかすで嗅覚を混乱させる!2日ごとの交換を推奨
- 金属音で近づきにくい環境づくり!風鈴の活用術
- 竹酢液の定期散布!週1回の頻度がポイント
柑橘系の香りで寄せ付けない!ミカンの皮活用法
みかんの皮から出る香りには、イタチを遠ざける効果があるんです。「この匂い、なんだか近寄りたくないな」とイタチが感じる成分が含まれているからです。
特に軒下やベランダ、庭先など、イタチが通りそうな場所に置くと効果的です。
みかんの皮は皮の内側を上に向けて置くのがポイント。
香りが上に広がって、より効果を発揮します。
置き方にも工夫が必要です。
- 皮は2センチ幅に切り分ける
- 3メートルごとに1つずつ配置する
- 3日ごとに新しいものと交換する
- 雨に濡れないよう、屋根のある場所を選ぶ
でも実は、柑橘系の香りにはイタチの鼻を混乱させる成分が含まれているのです。
みかんがない時期は、レモンやかぼすの皮でも代用できます。
ただし、梅雨時期は湿気で腐りやすいので、2日に1回の交換がおすすめ。
「こまめな交換が面倒...」という場合は、乾燥させた皮を使うと1週間持ちます。
赤色照明で侵入を防ぐ!100ルーメン以上の設置がコツ
赤い光には、イタチを寄せ付けない効果があります。「なぜ赤い光が効くの?」それは、イタチの目が赤色光に特に敏感な構造をしているからなんです。
設置場所は、イタチが侵入しそうな場所を中心に選びましょう。
- 玄関やベランダの入り口付近
- 庭と家をつなぐ通路沿い
- 物置や倉庫の周辺
- フェンスや塀の上部
暗すぎると効果が薄れてしまいます。
「まぶしすぎて近所迷惑にならない?」と心配な方も多いはず。
でも大丈夫。
赤色光は人の目にはそれほどまぶしく感じないんです。
照射時間は日没から夜明けまで。
特に夜8時から深夜2時は、イタチが最も活発に動き回る時間帯。
この時間帯は必ず点灯させておくことが大切です。
電気代が気になる方には、人感知式の赤色照明がおすすめ。
イタチが近づいたときだけ光る仕組みで、節電効果もばっちりです。
コーヒーかすで嗅覚を混乱させる!2日ごとの交換を推奨
コーヒーかすには、イタチの敏感な鼻を混乱させる力があります。「どうして効果があるの?」それは、コーヒーの香りに含まれる苦味成分がイタチの嗅覚を刺激するからなんです。
使い方は意外と簡単です。
- 乾燥させたかすを小皿に盛る
- 5メートルおきに設置する
- 2日ごとに新しいものと交換する
- 雨に濡れない場所を選ぶ
「面倒くさそう...」と思われるかもしれませんが、新聞紙の上に広げて半日ほど置くだけでOK。
湿ったままだと、すぐにかびてしまうので要注意です。
設置場所は、イタチの通り道となりやすい場所を狙います。
玄関先や庭の入り口、物置の周りなどがおすすめ。
特に、巣に向かう経路を予測して置くのが効果的です。
コーヒーかすは地面に直接まくのもよし、網袋に入れて吊るすのもよし。
使い方は自由自在なんです。
ただし、雨に濡れると効果が急激に落ちてしまうので、屋根のある場所での使用がベストです。
金属音で近づきにくい環境づくり!風鈴の活用術
風鈴のチリンチリンという音には、イタチを遠ざける効果があるんです。「なぜ風鈴なの?」それは、イタチが金属の高い音を特に苦手とするからです。
設置のポイントは、音が途切れないようにすること。
- 風通しの良い場所を選ぶ
- 3メートルごとに1つ設置する
- 地面から1メートルの高さに吊るす
- 複数の風鈴を違う高さに配置する
「風がないときは効果がないのでは?」そんな心配も大丈夫。
細い針金を風鈴に取り付けておけば、わずかな空気の動きでも音が鳴るようになります。
材質は真鍮製がベスト。
アルミや鉄製も使えますが、澄んだ高音が出る真鍮が最も効果的です。
サイズは直径5センチ程度のものを選びましょう。
大きすぎると近所迷惑になってしまいます。
風鈴を使う時期は、イタチが最も活発になる春から秋がおすすめ。
冬は音が凍りつくことがあるので、室内に取り込んで保管しましょう。
竹酢液の定期散布!週1回の頻度がポイント
竹酢液には、イタチを寄せ付けない成分が含まれています。「どんな仕組みなの?」それは、竹酢液の独特の刺激臭がイタチの嗅覚を刺激するからです。
使用方法は以下の手順で。
- 原液を10倍に薄める
- 霧吹きで細かく散布する
- 週1回のペースで繰り返す
- 雨の後は追加で散布する
特に、庭と家をつなぐ通路や、物置の周り、フェンスの下など、イタチの移動経路となりやすい場所を重点的に。
「竹酢液って安全なの?」という疑問も多いはず。
でも心配いりません。
土に染み込んでも植物や土壌には悪影響を与えないんです。
むしろ、土壌改良効果があるくらい。
ただし、散布時は風向きに注意。
風上から風下に向かって散布すると、目に入ったり服に付いたりする可能性があります。
必ず風下から風上に向かって散布しましょう。
イタチ対策の重要ポイント

- 湿度70%以上の場所は要注意!換気と除湿を徹底
- 生ゴミ放置は最大の誘引!即日処理を心がけよう
- 春と秋は特に警戒!繁殖期の活動が1.5倍に
湿度70%以上の場所は要注意!換気と除湿を徹底
イタチは湿度の高い場所を好んで生活します。このため、湿度70%以上の場所は特に警戒が必要なんです。
住宅の湿気対策をしっかり行えば、イタチの侵入を防ぐことができます。
「どうして家の中にイタチが?」と不安になる前に、まずは住環境を見直してみましょう。
- 天井裏や床下の換気口を24時間開放する
- 換気扇を1日3回以上稼働させる
- 除湿機で湿度を60%以下に保つ
- 雨漏りはすぐに修理して、すみずみまで乾燥させる
生ゴミ放置は最大の誘引!即日処理を心がけよう
生ゴミの放置は、イタチを引き寄せる原因の第一位です。「明日まで置いておこう」という考えは、イタチを招く最悪の選択になってしまいます。
生ゴミからぷんぷんと漂う匂いは、半径30メートルまで届くため要注意です。
- 生ゴミはその日のうちに処理する
- ゴミ箱は密閉式のものを使用する
- ゴミ置き場は毎日掃除して清潔に保つ
- 食べ残しを屋外に放置しない
春と秋は特に警戒!繁殖期の活動が1.5倍に
春と秋はイタチの繁殖期。この時期は通常の1.5倍も活発に行動するため、被害も増加しやすくなります。
「今までは大丈夫だったのに」という油断は禁物です。
繁殖期のイタチは、餌を求めて活動範囲を広げます。
- 活動範囲が普段の2倍に拡大
- 捕食量が通常の1.5倍に増加
- 夜間の活動が3時間以上延長
- 侵入経路の探索行動が活発化