イタチ対策フェンスの設置方法【高さ2メートル以上が必要】耐久性10年の補強術と95%の防御率

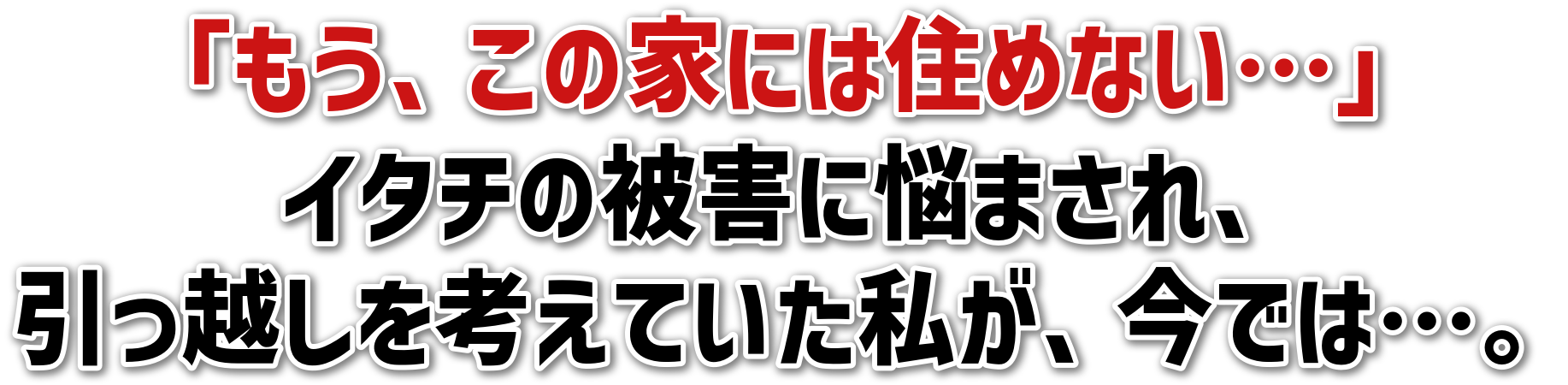
【疑問】
イタチ対策フェンスの設置で最も重要なポイントは?
【結論】
高さ2メートル以上の金属製メッシュを30センチごとに堅固に固定することです。
ただし、地中への50センチの埋め込みと斜め設置の工夫で、防御率を95%まで高められます。
イタチ対策フェンスの設置で最も重要なポイントは?
【結論】
高さ2メートル以上の金属製メッシュを30センチごとに堅固に固定することです。
ただし、地中への50センチの埋め込みと斜め設置の工夫で、防御率を95%まで高められます。
【この記事に書かれてあること】
イタチの被害に悩まされている方に、朗報です。- 設置高さは2メートル以上で地中には50センチの埋め込みが必要
- 支柱間隔は2メートルごとにコーナー部は1.5メートル間隔で補強
- メッシュは金属製を選び30センチごとに堅固な固定を実施
- 斜め設置で防御率95%まで向上させることが可能
- 5つの補強テクニックで長期的な忌避効果を実現
実は、フェンスの設置方法を工夫するだけで、イタチの侵入を95%以上防げるんです。
「でも、本当にフェンスだけで大丈夫なの?」そんな不安を持つ方も多いはず。
今回は、イタチ対策フェンスの正しい設置方法をご紹介します。
高さ2メートル以上の金属メッシュと、地中への埋め込み、そして耐久性を高める補強術まで。
10年以上効果が持続するフェンス設置のコツをお教えしましょう。
【もくじ】
イタチ対策フェンスの基本的な知識

- 侵入防止に必要な高さ「2メートル以上」が基本!
- 地中への掘り進み対策も万全に!深さ50センチが目安
- プラスチック製フェンスはNG!金属メッシュを選択
侵入防止に必要な高さ「2メートル以上」が基本!
イタチ対策フェンスは高さ2メートル以上が必須です。なぜなら、イタチは驚くほど高く跳び上がる力を持っているからです。
「うちのフェンスは1メートルもあるから大丈夫でしょ」なんて考えていませんか?
実はイタチは垂直に1メートル以上跳び上がることができる身軽な動物なんです。
さらに、体をくねらせながら器用によじ登る特技も持っているため、低いフェンスではすいすいと乗り越えてしまいます。
では具体的にどのような高さが必要なのでしょうか。
- 一般的な場所:地上から2メートル以上
- 建物近く:2.5メートル以上
- 樹木付近:3メートル以上
「えいっ」と跳びついた後に、壁や枝を足場にして更に上へと移動できてしまうため、通常より高めの設置が欠かせません。
「少し低くても大丈夫かな」と妥協は禁物。
必ず推奨される高さを確保しましょう。
上部を内側に30度以上傾斜させる工夫もおすすめです。
この方法なら全体の高さを1.8メートルまで抑えることができ、見た目もすっきり。
費用も2割ほど節約できるというわけです。
地中への掘り進み対策も万全に!深さ50センチが目安
イタチ対策フェンスの地中部分は深さ50センチ以上の埋め込みが必要です。地上部分だけでなく、地中への対策も重要なポイントなのです。
イタチは地面を掘り進むのが得意で、ちょっとした隙も見逃しません。
「きょろきょろ」と周囲を確認した後、前足でさっさと土を掘り始めます。
わずか10分ほどで直径10センチの穴を掘ることができるんです。
地中部分の防御には、次の3段階の対策が効果的です。
- 深さ50センチ以上の埋め込み:基本となる防御ライン
- コンクリート基礎の設置:掘り進みを物理的に阻止
- 砂利の敷き詰め:足場を不安定にして掘り進みを防止
これを敷き詰めることで、イタチが掘り進もうとしても「がさがさ」と砂利が崩れて足場が安定しません。
「ここは掘れないぞ」とイタチが諦めてくれるんです。
プラスチック製フェンスはNG!金属メッシュを選択
イタチ対策フェンスの素材は金属製メッシュが最適です。安価なプラスチック製は3ヶ月で劣化して破られる危険があるため、絶対に使用してはいけません。
耐久性の高い金属製メッシュには、以下の特徴があります。
- 網目の大きさ:1センチ以下
- 線の太さ:1.2ミリ以上
- 表面処理:溶融亜鉛メッキ加工
実はイタチの子どもは体が柔らかく、5ミリほどの隙間があれば「するっ」と通り抜けてしまうんです。
網目が粗いと、子イタチが侵入して成長した後、完全な住み着きを許してしまう可能性があります。
また、紫外線に弱いプラスチック製は「ぼろぼろ」と劣化が進み、イタチに「がじがじ」と噛み切られてしまいます。
「値段が安いからいいや」という選択は、結果的に高くつくことになるのです。
金属製メッシュなら10年以上の耐久性があり、長期的な防御が可能になります。
強度と耐久性を確保する設計のポイント

- 支柱間隔は2メートルごとが最適!コーナー部は要補強
- メッシュは30センチごとに堅固な固定が必須!
- 基礎工事で10年以上の耐用年数を実現!
支柱間隔は2メートルごとが最適!コーナー部は要補強
支柱の間隔は2メートルごとが最も効果的です。この間隔なら風圧にもびくともしません。
設置する際は、次の3つのポイントに気をつけましょう。
- 支柱は地面にぐらつきなく、しっかりと固定する
- コーナー部分は1.5メートル間隔で支柱を増やす
- 支柱と支柱の間にたるみができないよう、張り具合を調整する
イタチはちょっとした隙間も見逃しません。
コーナー部分は力がかかりやすく、たるみが出やすい場所なんです。
支柱の間隔を狭めることで、がっちりと補強できます。
メッシュは30センチごとに堅固な固定が必須!
メッシュの固定には、30センチごとの取り付けが欠かせません。専用の固定金具をきちんと使って、しっかりと留めましょう。
継ぎ目の処理も重要です。
- 継ぎ目は10センチ以上重ねて固定する
- 結束線は2重に巻いてがっちり固定する
- 固定金具は錆びにくい素材を選ぶ
- 上部と下部は特に念入りに固定する
基礎工事で10年以上の耐用年数を実現!
基礎工事をしっかり行えば、10年以上の耐用年数を確保できます。大切なのは、次の工事手順です。
- 掘削の深さは80センチまで掘り下げる
- 砕石を敷き詰めて地盤をしっかり固める
- 支柱の周りに生コンクリートを流し込む
- コンクリートは完全に固まるまで3日間放置する
ていねいな工事で、長持ちするフェンスに仕上げましょう。
取付方法で分かれる効果と費用
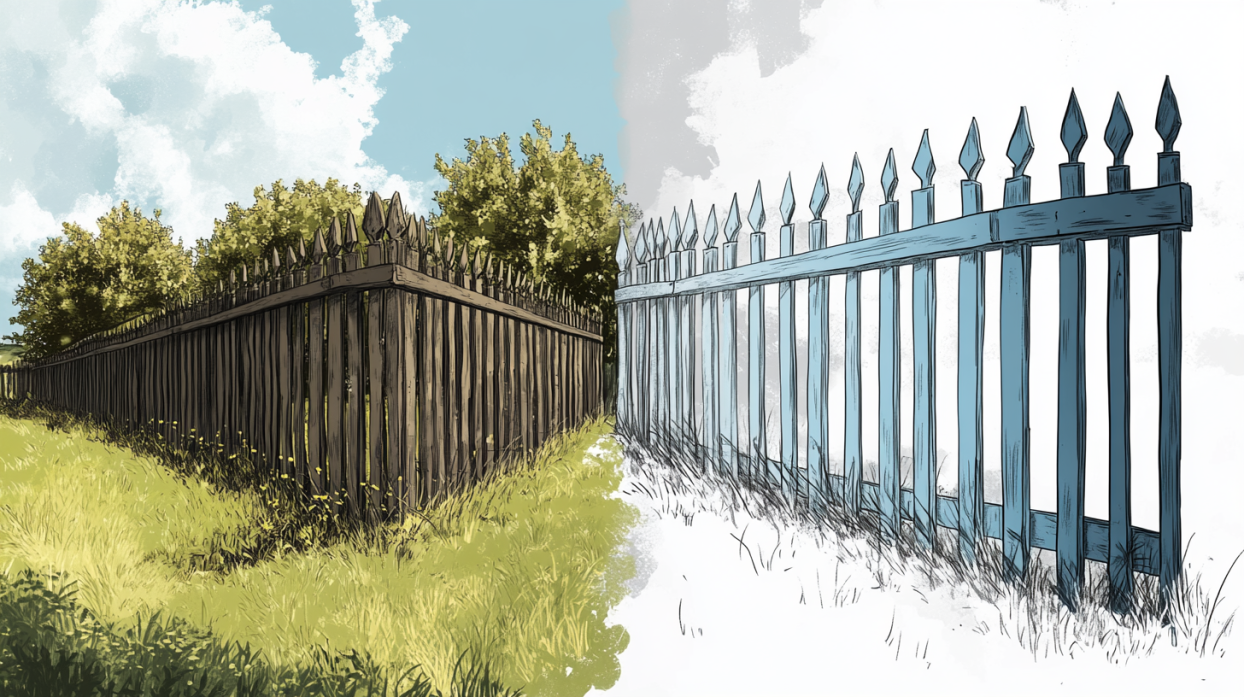
- 既存フェンスvs新設フェンス!耐久性は3倍の差
- 単管パイプvs専用支柱!設置時間が半分に短縮
- 直線設置vs斜め設置!防御率95%の違い
既存フェンスvs新設フェンス!耐久性は3倍の差
既存のフェンスにイタチ対策用の金網を取り付けるか、新しくフェンスを設置するか。結論から言うと、費用は2倍かかりますが、新設がおすすめです。
「既存のフェンスを活用すれば費用が抑えられるのでは?」と考えがちですが、要注意です。
既存フェンスへの取り付けには、がっちりした支柱がないため、ぐらぐらと不安定になってしまうんです。
新設の場合は、地中にしっかりとした基礎を作れるため、耐久性が3倍以上になります。
「どうせやるなら確実に!」という方におすすめの方法です。
- 既存フェンス活用のデメリット:支柱が細くて不安定、地中への掘り進み防止ができない、3年程度で歪みが出る
- 新設フェンスのメリット:基礎工事でびくともしない安定感、地中部分まで完全防御が可能、10年以上の耐久性
- 費用の目安:既存活用は3万円から、新設は6万円からスタート
単管パイプvs専用支柱!設置時間が半分に短縮
支柱の選び方で迷った時は、価格が3割高くても専用支柱がおすすめです。作業時間が半分で済み、強度も2倍以上あります。
単管パイプは安価で手に入りやすい反面、がたがたと振動が出やすく、イタチに揺すられると簡単にぐらついてしまうんです。
「費用を抑えたいな」と思っても、後々の補修で結局お金がかかってしまいます。
専用支柱は太さが十分あり、表面加工も施されているため、すっと素早く設置できます。
- 単管パイプの特徴:価格が安い、現場で長さ調整が可能、設置に技術が必要
- 専用支柱の特徴:ガッチリした安定感、簡単な工具で組み立て可能、メッシュとの相性が抜群
- 作業時間の比較:単管パイプは6時間、専用支柱は3時間で完了
手間なく確実な防御を実現できます。
直線設置vs斜め設置!防御率95%の違い
フェンスの設置角度で迷ったら、費用は2割増しですが斜め設置を選びましょう。イタチの侵入防止率が95%まで上がります。
直線設置は一般的ですが、イタチは器用に登り降りしてしまいます。
「まっすぐ立てれば大丈夫」と思いがちですが、それは大きな誤解。
イタチは垂直な壁面を簡単によじ登れるんです。
斜め設置なら、内側に30度以上傾けることで、イタチの動きを封じ込めることができます。
- 直線設置の欠点:よじ登りやすい形状、設置後の補強が難しい、防御率は70%程度
- 斜め設置の利点:背面からの侵入を防止、耐久性が1.5倍に向上、見た目もすっきり
- 設置角度の目安:地面から30度以上傾けると効果的
5つの画期的な補強テクニック

- 支柱内側に「猫の爪とぎシート」で寄せ付けない!
- フェンス上部に「風車」設置で威嚇効果アップ
- メッシュ結び目に「ミント油」で長期的な忌避を実現
- 支柱周りに「反射テープ」で夜間の接近を防止
- 地際に「粗目の砂利」で掘り進みをブロック!
支柱内側に「猫の爪とぎシート」で寄せ付けない!
イタチ対策フェンスの支柱に猫の爪とぎシートを巻き付けると、イタチの警戒心を刺激して寄せ付けなくなります。「どうして爪とぎシートが効くの?」と思われるかもしれません。
実はイタチは、猫の存在を示す痕跡に対して本能的に警戒心を抱くんです。
爪とぎシートを取り付ける際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- シートは地上30センチから高さ2メートルまでの範囲に巻く
- 支柱1本につき幅10センチのシートを2周分使用する
- 雨に濡れても剥がれないよう防水テープで上下を固定する
- 3ヶ月ごとに新しいシートに交換して効果を持続させる
「どの高さに付ければいいの?」というお悩みには、こんな例えで考えるとわかりやすいでしょう。
お店の看板は目線の高さに付けますよね。
それと同じで、イタチの目線である地上30センチから順に巻いていくのがコツなんです。
シートはホームセンターで手に入る一般的な物で十分です。
ただし、香りの強すぎる物は逆効果。
無香料タイプを選びましょう。
こうして猫の存在を匂わせることで、イタチは「ここは危険だぞ」と感じて近寄らなくなっちゃうんです。
フェンス上部に「風車」設置で威嚇効果アップ
ペットボトルで作った風車をフェンス上部に取り付けると、回転音と動きでイタチを効果的に威嚇できます。「子どもの理科の工作みたい」と思われるかもしれません。
でも、これが意外と効果てきめんなんです。
クルクルと回る風車の動きと、キュッキュッという回転音が、イタチの警戒心を刺激します。
設置のコツは以下の通りです。
- 2リットルのペットボトルを横向きに半分に切る
- 羽根は幅5センチ、長さ15センチで8枚作る
- 支柱の頭部から30センチ下がった位置に設置する
- 取り付け間隔は2メートルごとが目安
- 強風で飛ばされないよう金具でしっかり固定する
ペットボトルは透明な物を選びましょう。
「太陽の光を反射させて、さらに効果アップ!」というわけです。
風車は3ヶ月ごとに新品に交換します。
紫外線で劣化して色が曇ってきたら、交換時期の目安です。
きれいな風車がキラキラ光りながら回る様子は、まるで「ここは立ち入り禁止だよ」と警告を発しているかのよう。
イタチもビクビクしながら遠巻きに見ているはずです。
メッシュ結び目に「ミント油」で長期的な忌避を実現
メッシュの結び目にミント油を染み込ませることで、イタチの嫌う香りで長期的な忌避効果を得られます。「どんなミント油を選べばいいの?」という疑問には、こんなポイントがあります。
- 天然の和種ハッカ油を選ぶ
- 原液を10倍に薄めて使用する
- 小さな霧吹きを使って細かく噴霧する
- 週1回の補充で効果を維持する
メッシュの結び目に集中的に染み込ませることで、風に揺られるたびに香りが広がる仕組みを作りましょう。
まるで「立ち入り禁止の結界」のような効果が生まれるんです。
ここで気をつけたいのが使用量です。
強すぎる香りは近隣への迷惑になりかねません。
「お香をたいているお寺」くらいの控えめな香りを目安にしましょう。
効果を長持ちさせるコツは、雨の日を避けて塗布すること。
また、日が当たる場所は香りが飛びやすいので、夕方以降に補充するのがおすすめです。
こうして、イタチは「この場所は危険だぞ」と感じて、スーッと遠ざかっていくというわけです。
支柱周りに「反射テープ」で夜間の接近を防止
支柱に反射テープを巻き付けることで、夜間のイタチの接近を効果的に防止できます。テープの選び方と取り付け方は以下の通りです。
- 幅5センチの反射材を使用する
- 支柱1本につき3本の帯状に巻く
- 地上から30センチごとに設置する
- 斜め45度の角度で巻き付ける
- 3ヶ月ごとに新しいテープに交換する
車のライトや街灯の光が当たったとき、斜めの反射面が作る不規則な光の動きが、イタチの目をキラキラと惑わせます。
まるで「目が回っちゃいそう」な状態に。
夜行性のイタチにとって、この予測できない光の反射は非常に警戒すべき現象なんです。
「ここは危険がいっぱい!」と感じて、自然と遠回りする習性を利用した技なんです。
地際に「粗目の砂利」で掘り進みをブロック!
フェンスの地際に粗目の砂利を敷き詰めることで、イタチの掘り進みを効果的に防ぐことができます。砂利選びのポイントは以下の通りです。
- 粒径5センチ以上の大きな石を選ぶ
- 角の尖った形状の物を使用する
- 深さ30センチまで敷き詰める
- 幅50センチの帯状に配置する
実は、イタチは柔らかい土を好んで掘るんです。
ゴロゴロした大きな石が混ざっていると、爪が引っかかってスムーズに掘れません。
砂利を敷く範囲は、フェンスの内側と外側の両方にL字型に配置するのがコツ。
これにより、イタチは「この地面は掘れそうにないぞ」と判断して、掘り進みを諦めてしまうんです。
まるで「天然の防護壁」のような役割を果たしてくれます。
設置時の重要な注意事項

- 地下水脈を避けた掘削で基礎の強度を確保!
- 日照と視界を妨げない「設置位置」の選定ポイント
- 積雪地域では「支柱間隔を狭める」で耐久力アップ!
地下水脈を避けた掘削で基礎の強度を確保!
地下水脈の上に支柱を立てると、基礎が弱くなって倒れやすくなってしまいます。「せっかく設置したのに数ヶ月で傾いてきた…」なんてことにならないよう、事前の調査が大切です。
- 敷地内の湧き水が出る場所を探してみましょう
- 雨の日に水がたまりやすい場所をチェックしましょう
- 地面がふかふかして柔らかい場所は要注意です
- 湿った土の場所は掘削位置を30センチずらしましょう
ぐにょぐにょと沈み込む場所は、地下水脈が流れている可能性が高いんです。
そんな場所は避けて、がっちりした地盤を選びましょう。
日照と視界を妨げない「設置位置」の選定ポイント
フェンスの設置場所によっては、近所とのトラブルのもとに。「庭に日が当たらなくなった」「車の出し入れが見づらい」といった苦情を防ぐため、位置選びは慎重に行いましょう。
- お隣の窓から2メートル以上離して設置します
- 車の出入り口から3メートル以上の距離を確保します
- 植木や花壇への日当たりを考慮して配置します
- 道路からの見通しを遮らない高さを選びます
近隣への配慮を忘れずに。
積雪地域では「支柱間隔を狭める」で耐久力アップ!
雪の重みでフェンスがぐにゃりと曲がってしまわないよう、支柱の間隔を通常よりも狭めに設置します。「去年の大雪でペシャンコになっちゃった」なんて失敗を防ぐため、積雪への対策は必須です。
- 支柱の間隔を1.5メートルまで縮めましょう
- 支柱の太さを1.5倍にして強度を上げます
- 雪が積もりにくい傾斜を付けた天板を取り付けます
- メッシュの固定具を20センチ間隔に増やします