イタチの大きさはどのくらい?【体長20センチ前後のオスが多い】隙間侵入を防ぐ5つの対策法

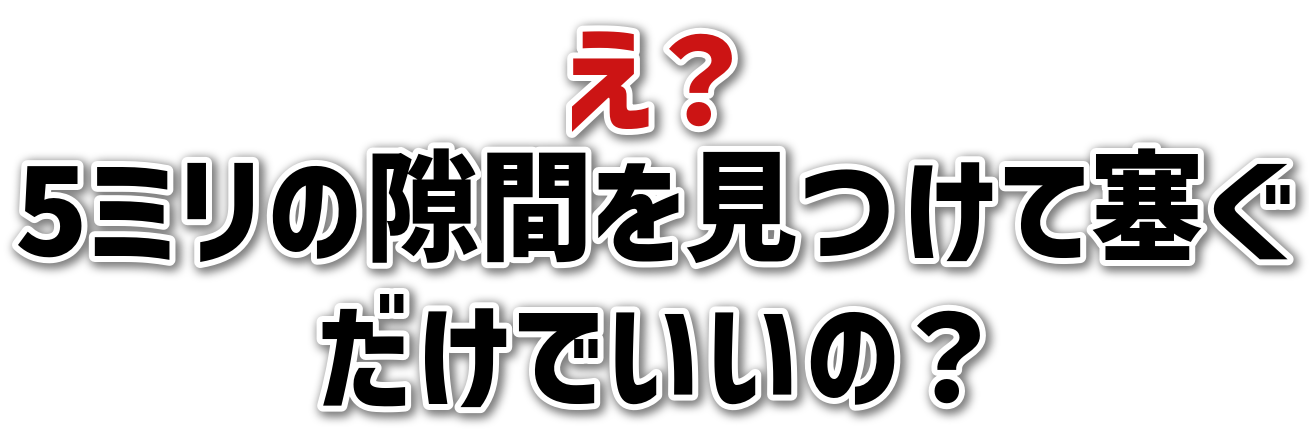
【疑問】
イタチはどれくらいの隙間から侵入できるの?
【結論】
体を扁平にして5ミリ以上の隙間から侵入できます。
ただし、冬毛の時期は体が太くなるため、7ミリ以上の隙間に注意が必要です。
イタチはどれくらいの隙間から侵入できるの?
【結論】
体を扁平にして5ミリ以上の隙間から侵入できます。
ただし、冬毛の時期は体が太くなるため、7ミリ以上の隙間に注意が必要です。
【この記事に書かれてあること】
家の中に住み着いたイタチの侵入口が見つからない…。- オスは体長20センチ前後でメスより大きな体格
- 胴回りは最小6センチから最大10センチまで変化
- 扁平な頭部構造で小さな隙間から侵入可能
- 冬は体重が2割増加し体格が変化
- 段ボールや砂を使った5つの実践的な対策法で侵入を防止
その原因は、イタチの体の大きさを誤解しているからかもしれません。
体長20センチの小さな体は、わずか5ミリの隙間さえも通り抜けられるのです。
成獣のオスとメスでは体格が大きく異なり、季節によっても体の太さが変化します。
「これくらいの隙間なら大丈夫」という思い込みが、イタチ被害を招く結果に。
今回は、イタチの体格を徹底解説し、隙間侵入を防ぐ具体的な対策法をご紹介します。
【もくじ】
イタチの大きさを正確に把握しよう

- イタチの体長20センチ!オスとメスで大きさが異なる実態
- 胴回り最小6センチから最大10センチ!伸縮する体の特徴
- イタチの頭部は「扁平な形状」で隙間侵入に要注意!
イタチの体長20センチ!オスとメスで大きさが異なる実態
イタチのオスとメスには大きな体格差があり、オスは体長20センチ、メスは15センチ程度です。「うちに来るイタチ、どのくらいの大きさなんだろう?」そんな疑問を持つ方は多いはず。
実は、イタチの体の大きさは性別によってくっきりと違います。
オスの体は、定規で測ると頭からしっぽの付け根まで約20センチ。
一方メスは約15センチで、まるで体型が違うんです。
これは、自然界での役割分担が関係しています。
- オス:体重450グラムで、がっしりした体格
- メス:体重250グラムで、すらりとした体型
- オスは縄張り争いのため、メスは子育てのための体格
オスは「他のオスと戦わなきゃ」「獲物を捕まえなきゃ」という役割があるため、どうしても大きな体が必要なんです。
一方メスは「子育ての巣穴に出入りしやすく」「狭い場所でも動きやすく」という理由から、すらっとした体になっているというわけ。
体格差は春から秋にかけて最も顕著です。
「この差が分かれば、オスかメスか見分けやすくなりますよ」と、まさにぴったり。
胴回り最小6センチから最大10センチ!伸縮する体の特徴
イタチの胴回りは、なんとゴムのように伸び縮みして6センチから10センチまで変化します。イタチの体には、とても不思議な特徴があるんです。
それは、まるでスポンジのように体が伸び縮みすること。
胴回りは、細いところでぷにっと6センチ、太いところでぽってり10センチもあります。
「どうしてそんなに変化するの?」それは、イタチの体の構造に秘密が。
骨格がしなやかで、筋肉がよく発達しているため、体を自在に変形できるんです。
- 細い時:すらっと6センチで、隙間もすいすい
- 普通の時:ふっくら8センチで、普段の生活
- 太い時:むちっと10センチで、冬毛や食後に
「ここは通れないかな?」と思える隙間も、くにょんと体を変形させて、するっと通り抜けてしまいます。
まさに「忍者のような体の使い手」。
この能力があるからこそ、小さな隙間からも家に侵入できてしまうのです。
イタチの頭部は「扁平な形状」で隙間侵入に要注意!
イタチの頭部は横幅4センチ、縦幅3センチの扁平な形で、この形状が隙間侵入を可能にしています。「イタチはどうやって隙間から入ってくるの?」その答えは、頭の形にあります。
イタチの頭は、上から見るとぺったんこな形をしているんです。
この扁平な頭の特徴は、隙間侵入の重要なポイント。
なぜなら、イタチは「頭が通れば体も通れる」という習性を持っているからです。
- 頭の横幅:にょろっと4センチで横長
- 頭の縦幅:ぺったり3センチでつぶれ気味
- 頭の形状:まるで薄型の楕円形
「こんな小さな隙間、通れるはずがない」と思っても、つるんと通り抜けてしまうことも。
そのため、家の周りの小さな隙間も、イタチには立派な通り道になってしまうんです。
イタチの体格を季節と時間帯で理解

- 冬は体重が2割増加!季節による体格変化のメカニズム
- 夜間は体を最大限伸ばして行動!活動時の寸法変化
- 繁殖期は体が太くなる!メスの体格変化に注目
冬は体重が2割増加!季節による体格変化のメカニズム
イタチの体重は寒い季節になると約2割も増えるんです。これは寒さから身を守るための自然な変化です。
体の変化を詳しく見ていきましょう。
- 夏から秋にかけて、体重が徐々に増加
- 冬毛が生えそろう時期に、胴回りが最大10センチまで太くなる
- 寒さが厳しくなると、体脂肪が通常の1.5倍に増える
- 春になると、約3週間かけて通常の体格に戻る
夜間は体を最大限伸ばして行動!活動時の寸法変化
日が沈むと、イタチの体は思い切り伸びるんです。夜行性のイタチは、暗闇での行動時に体を最大限に伸ばして活動します。
- 体を伸ばすと、通常より長さが1.5倍に
- 胴回りは反対に6センチまで細くなる
- 頭部も上下に押しつぶされて高さ2センチまで薄くなる
- 関節の隙間が広がり、くねくねと自由自在に動く
繁殖期は体が太くなる!メスの体格変化に注目
繁殖期に入ると、メスの体格がぐんぐん変化します。特に出産が近づくと、体の変化が顕著になってきます。
- おなかの周りが通常の1.5倍まで大きくなる
- 体重は最大で2倍近くまで増加
- 胸回りも8センチから12センチに拡大
- 尾の付け根がふっくらと太くなる
イタチと他の動物の体格を徹底比較

- イタチvsテン!体長差15センチの圧倒的な違い
- イタチvsフェレット!ペットとの体格差を確認
- イタチvsネズミ!体重差で分かる捕食能力の高さ
イタチvsテン!体長差15センチの圧倒的な違い
テンはイタチの1.5倍もの体格があり、体の作りにも大きな違いがあります。「イタチと同じ仲間なのに、こんなに違うの?」そう思われる方も多いはず。
テンの体長は35センチもあり、イタチより15センチも長いんです。
体重も900グラムと、イタチの2倍の重さがあります。
その体格差は、まるで小学1年生と6年生くらいの違いです。
体の特徴も異なっていて、テンの体はがっしりとした筋肉質。
一方イタチは細長くてすらっとしています。
- テンの胴回りは15センチで、イタチの1.5倍
- テンの頭部は横幅6センチで、イタチの1.5倍
- テンの脚は5センチで、イタチより2センチ長い
テンは木の上で生活することが多く、太い枝を走り回れる体格が必要なんです。
一方イタチは地上や建物の狭い場所で暮らすため、細長い体型の方が都合がいいというわけです。
イタチvsフェレット!ペットとの体格差を確認
フェレットはイタチより一回り大きな体格を持っています。家畜化の過程で体格が大きくなったのが理由です。
体長はフェレットが25センチで、イタチより5センチ長いんです。
体重も700グラムと、イタチより250グラム重たくなっています。
「まるで、小学生と中学生くらいの違いかな」そんなイメージです。
- フェレットの胴回りは12センチで、イタチより2センチ太い
- フェレットの頭部は横幅5センチで、イタチより1センチ大きい
- フェレットの脚は4センチで、イタチより1センチ長い
野生のイタチは細い隙間を自由に通り抜けられる必要がありますが、ペットのフェレットはそこまでの身のこなしは必要ありません。
そのため、フェレットは体格が大きくなり、動きもゆっくりめ。
でも、イタチのような身軽さはないものの、飼いやすい体格になっているんです。
イタチvsネズミ!体重差で分かる捕食能力の高さ
イタチとネズミの体長は同じくらいですが、体の作りには大きな違いがあります。それがイタチの捕食能力の高さにつながっているんです。
クマネズミの体長は20センチで、イタチとほぼ同じです。
でも体重は200グラムと、イタチの半分以下。
「同じ長さなのに、なんでこんなに軽いの?」その理由は、体の作りが全然違うからなんです。
- イタチの体は筋肉質で引き締まっている
- ネズミの体は柔らかくてふんわりしている
- イタチの骨格は頑丈でがっしりしている
まるで、同じ身長の相撲取りとマラソン選手を比べるような違いです。
イタチの体は狩りに適した作りになっていて、ネズミを捕まえるのも「ぺろっと一息」というわけです。
イタチの侵入を防ぐ5つの実践的対策

- 段ボールで簡単チェック!通り抜け実験で侵入口を発見
- 新聞紙を活用!足跡から成獣か幼獣かを判別する方法
- 砂の活用法!通過跡から体の変形具合を確認するコツ
- 石膏で型取り!実際の侵入経路の大きさを測定する技
- 竹ひごを使用!隙間の奥行きを正確に把握する方法
段ボールで簡単チェック!通り抜け実験で侵入口を発見
段ボールを使った簡単な実験で、イタチが通り抜けられる隙間の大きさを正確に把握できます。まずは段ボールに直径5ミリの穴を開けてみましょう。
「えっ、こんな小さな穴を通れるの?」と思うかもしれませんが、イタチの体は驚くほど柔軟なんです。
実験のコツは3つあります。
- 穴は必ず真円に開ける
- 段ボールは厚さ5ミリ以上のものを使う
- 穴の大きさは0.5ミリずつ変えて複数作る
実験では、直径5ミリの穴がスーッと通り抜けられれば、その大きさの隙間は要注意。
「うちの壁にこんな隙間あったかも!」という発見にもつながります。
特に気を付けたいのは配管まわり。
配管と壁の間にできた隙間は、見た目より広がっていることが多いものです。
実験結果を参考に、きゅっと目を凝らして確認してみましょう。
新聞紙を活用!足跡から成獣か幼獣かを判別する方法
新聞紙を使えば、イタチの足跡から侵入個体の年齢を見分けることができます。これは対策の優先順位を決める重要な手がかりとなります。
新聞紙は玄関マットの下に敷くのがおすすめ。
「なぜ玄関マット?」それは、イタチが家の周りを探索するとき、必ずといっていいほど立ち寄る場所だからです。
足跡を見分けるポイントは以下の通りです。
- 成獣の前足は幅2センチの丸型
- 幼獣の前足は幅1.5センチの細長型
- 足跡の間隔は成獣が15センチ、幼獣が10センチ
ぺたぺたと付いた足跡は、時間が経つとにじんでしまうことがあるからです。
「成獣の足跡があった!」という場合は要注意。
繁殖期のメスである可能性が高く、すばやい対策が必要になってきます。
「幼獣の足跡が見つかった!」場合も油断は禁物。
親イタチが近くにいる証拠かもしれません。
砂の活用法!通過跡から体の変形具合を確認するコツ
細かい砂を使えば、イタチの体がどこまで変形できるのか、その限界を知ることができます。まずは壁際に砂場用の砂を盛り、水を染み込ませます。
「砂はどのくらい湿らせればいいの?」という疑問には、にぎると形が残る程度が目安です。
イタチが通り抜けた跡を観察すると、体の変形具合が分かりやすく残ります。
- くびれた形の跡は体を細める場所
- 丸い形の跡は体を丸める場所
- 平らな跡は体を扁平にする場所
「ここまで体が変形できるのか!」と驚くはずです。
特に注目したいのは、砂の上に残った胴体の跡。
通常は6センチ幅なのに、にゅるっと3センチまで細くなった跡が見つかることも。
こんな風に体を変形させて、狭い隙間をすり抜けていくんです。
砂の実験で分かった変形具合を参考に、家の周りの隙間を探してみましょう。
体を変形させて通れそうな場所が、イタチの侵入経路になっているかもしれません。
石膏で型取り!実際の侵入経路の大きさを測定する技
石膏を使って隙間の型を取れば、イタチが実際に通っている経路の大きさが正確に分かります。まず石膏を水で溶いて、壁と柱の間の隙間に流し込みます。
「固まるまでどのくらい待てばいい?」という声が聞こえてきそうですが、冬場なら30分、夏場なら15分程度です。
石膏で型を取るときの注意点は3つ。
- 隙間の奥までしっかり流し込む
- 石膏は半分固まってから取り出す
- 隙間の表面を傷つけないよう慎重に
特に驚くのは、見た目は小さな隙間なのに、奥に行くほど広がっているケース。
こういう隙間こそ、イタチが好んで使う通り道なんです。
イタチは体を器用に曲げながら進むので、直線的な隙間より、くねくねと曲がった隙間を得意とします。
石膏の型を見れば、そんな侵入経路の特徴がはっきりと分かるというわけです。
竹ひごを使用!隙間の奥行きを正確に把握する方法
竹ひごを使えば、イタチが通れそうな隙間の奥行きを簡単に測ることができます。これは見落としがちな侵入経路を見つけるのに役立ちます。
竹ひごは太さ2ミリ程度のものを選びましょう。
「なぜ竹ひごなの?」それは、しなやかで折れにくく、隙間の形状に沿って曲がってくれるからです。
測定のコツは以下の通り。
- 竹ひごは少しずつ押し込む
- 途中で止まった場所をチェック
- 竹ひごの曲がり具合を確認
実は見えている隙間より、ずっと奥まで空間が続いているケースが多いんです。
特に要注意なのは、竹ひごがくるっと曲がって進む場所。
イタチは体を自在に曲げられるので、そういう曲がった隙間こそ、お気に入りの通り道になりやすいものです。
イタチ対策で見落としがちな重要ポイント

- メス出産時は体が1.5倍に!通常の対策では防げない危険
- 冬毛は夏毛より2センチ厚い!季節変化への備えが必須
- 若獣の体は親より細く柔軟!隙間対策の盲点に注意
メス出産時は体が1.5倍に!通常の対策では防げない危険
イタチのメスは出産時期になると、体が通常の1.5倍まで大きくなります。「この隙間なら大丈夫」と思っていても、予想以上の体格変化に要注意です。
メスの体格変化について、詳しく見ていきましょう。
- お腹周りが最大で15センチまで膨らむことも
- 体重は通常の2倍の500グラムを超えることも
- 胴体の長さも1.3倍の20センチまで伸びる
ぎゅうぎゅうと体を押し込んでくるので、通常の対策では防ぎきれないんです。
冬毛は夏毛より2センチ厚い!季節変化への備えが必須
イタチの毛の厚みは季節によって大きく変化します。冬になると毛が2センチも厚くなってしまうのです。
「夏場の対策をそのまま続けていれば安心」というのは大きな間違い。
- 夏の毛の厚みは5ミリ程度でぺたんこ
- 冬は毛が2センチの厚みでもこもこに
- 体の太さが見た目で4センチも違うことも
特に寒い地域では、冬場の体格変化への対策が必須というわけ。
若獣の体は親より細く柔軟!隙間対策の盲点に注意
若いイタチは成獣の半分以下の体格しかありません。そのうえ、骨がやわらかくて体が自由自在に曲がるんです。
「親が通れない隙間なら安全」は大きな誤解です。
- 体重はわずか100グラムでぺろりと軽い
- 胴回りは4センチしかなくすらりと細い
- 骨がやわらかく3ミリの隙間にも無理やり侵入
子育て時期は若獣の侵入にも気をつけましょう。