イタチの巣穴はどんな場所に?【地上3メートル以内が多い】5つの効果的な対策で撃退!

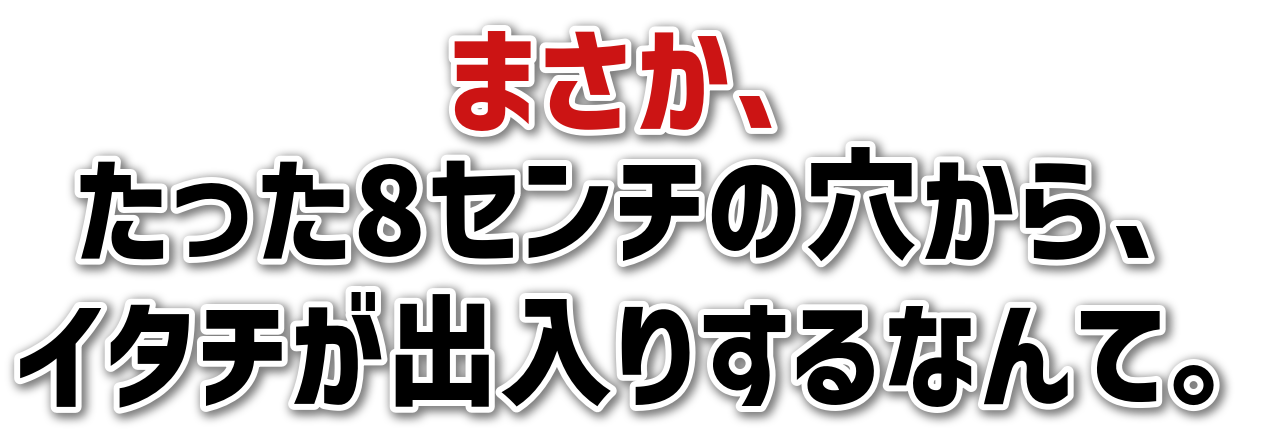
【疑問】
イタチの巣穴はどこにできやすいの?
【結論】
地上3メートル以内の日当たりが良く、水場に近い土手や崖下に巣穴を作る傾向があります。
ただし、餌となる小動物が豊富な場所であれば、人家の近くにも巣穴を作ることがあります。
イタチの巣穴はどこにできやすいの?
【結論】
地上3メートル以内の日当たりが良く、水場に近い土手や崖下に巣穴を作る傾向があります。
ただし、餌となる小動物が豊富な場所であれば、人家の近くにも巣穴を作ることがあります。
【この記事に書かれてあること】
イタチの巣穴を見つけた瞬間、焦る気持ちはよく分かります。- イタチの巣穴は直径8センチの円形の穴が特徴
- 巣穴は地上3メートル以内の日当たりの良い場所に作られやすい
- 水場から30メートル圏内の環境を好んで巣穴を作る
- 砂撒きや竹ぼうき設置など5つの効果的な対策で撃退可能
- 4月から6月は子育て期間のため慎重な対応が必要
「早く埋めてしまいたい」「すぐに駆除したい」という思いが頭をよぎりますよね。
でも、ちょっと待ってください。
イタチの巣穴には、実は見逃せない重要なポイントがあるんです。
地上3メートル以内の日当たりの良い場所に作られる傾向があり、直径8センチの円形の穴が特徴的。
巣穴の見つけ方と効果的な対策を知れば、イタチ被害から家を守ることができます。
【もくじ】
イタチの巣穴の場所をチェックしよう

- 地上3メートル以内の環境に特に要注意!
- 巣穴の大きさは「直径8センチの円形」が特徴
- 巣穴を埋めてしまうのはNG!リスクを知ろう
地上3メートル以内の環境に特に要注意!
イタチの巣穴は地上から3メートル以内の場所に作られやすく、特に地面から1メートルほどの高さが最も危険です。「どうしてうちの庭にイタチが?」と思われる方も多いはず。
実は、イタチは私たちの身近な場所に巣を作る習性があるんです。
- 土手や崖のような傾斜のある場所
- 建物の基礎と地面の間のすき間
- 石垣やブロック塀の隙間
特に気を付けたいのが、庭木の根元や物置の下といった場所。
「イタチなんて来ないだろう」と油断していると、いつの間にか巣が作られてしまうことも。
巣の入り口は複数作られることが多く、「ここから逃げられそう」という場所に予備の出入り口を用意します。
まさに「用心深い」という言葉がぴったり。
そのため、1つの巣穴を見つけたら、その周辺も丁寧に調べる必要があります。
巣穴の大きさは「直径8センチの円形」が特徴
イタチの巣穴は直径8センチほどの丸い穴が特徴で、まるでごろんと転がった缶ジュースが入りそうな大きさです。見分け方のポイントは、穴の形と周辺の様子。
イタチは器用に穴を掘るため、きれいな円形の穴になります。
周りには掘り出された土が山のように積まれ、その土の表面には爪で掻いた跡がくっきり。
- 穴の周りに小さな骨や毛が散らばっている
- 独特の臭いが漂う
- 地面に爪痕が残っている
- 巣の内部は奥行き50センチほど
「まるで高級マンションみたいだ」と言いたくなるほど、しっかりと作り込まれているんです。
内部は寝室やトイレなど、用途によって区画分けされ、床には枯れ草や落ち葉が敷き詰められています。
巣穴を埋めてしまうのはNG!リスクを知ろう
巣穴を見つけたら「すぐに埋めてしまおう」と考える方も多いですが、それは大変危険です。まずは中に子イタチがいないか確認が必要。
なぜなら、春から初夏にかけては子育ての時期。
「早く対処しなきゃ」という焦りから巣穴を埋めてしまうと、中にいる子イタチが生き埋めになってしまう可能性があるんです。
- 巣穴を埋めると新しい場所に巣を作る
- 子イタチがいると親イタチが攻撃的になる
- 慌てて埋めると予備の出入り口を見落とす
「もぐらたたき」のように、次々と新しい巣が作られてしまいます。
そのため、まずは巣の様子を観察することが大切。
足跡や行動パターンを把握してから、適切な対策を考えましょう。
イタチの巣穴が作られやすい環境の特徴

- 日当たりと水場が近い「土手や崖下」に要注意!
- 餌となる小動物が豊富な場所を選んで営巣
- 乾燥した場所に「複数の出入り口」を作る習性
日当たりと水場が近い「土手や崖下」に要注意!
イタチは人家から30メートル以内の、日当たりの良い土手や崖下を好んで巣穴を掘ります。特に南向きの斜面で、午前中に陽がしっかり当たる場所を選びます。
巣穴作りに最適な環境には、次のような特徴があるんです。
- 水場まで30メートル以内の距離にある場所
- 地面がさらさらと崩れやすい柔らかい土質の斜面
- 周囲に低い木や草むらが生い茂っている場所
- 人の往来が少なく静かな環境が保たれている場所
餌となる小動物が豊富な場所を選んで営巣
イタチは狩りに便利な場所を見極めて巣穴を作ります。1日3回の狩りが必要なため、餌となる小動物が豊富な環境を選ぶのです。
巣穴周辺には、次のような特徴が見られます。
- ネズミの生息を示す穴やフンの痕跡
- 小鳥の餌場や水飲み場がある環境
- カエルやトカゲが日向ぼっこをする岩や石
- 昆虫の発生源となる腐葉土や倒木
乾燥した場所に「複数の出入り口」を作る習性
イタチは賢い動物で、巣の安全性を高めるために複数の出入り口を作ります。メインの入口に加えて、2〜3個の非常口を別方向に設置するんです。
巣穴の構造には、こんな特徴があります。
- メイン入口は直径8センチの円形で整った形
- 非常口は少し小さめの直径6センチ程度
- 内部は乾燥した枯れ草を敷き詰めて保温
- トイレスペースは別の場所に確保
イタチの巣穴vsその他の動物の巣穴

- イタチとタヌキの巣穴「直径の違い」に注目!
- イタチvsネズミの巣穴「形状と周辺の特徴」
- イタチとテンの巣穴「作られる高さ」の比較
イタチとタヌキの巣穴「直径の違い」に注目!
タヌキの巣穴は直径30センチと大きいのに対し、イタチの巣穴は直径8センチと小さめです。この大きな違いで見分けることができます。
「この穴、イタチの巣かタヌキの巣か分からないな…」そんなときは、まず穴の大きさに注目してみましょう。
イタチの巣穴は、ちょうど子どもの握りこぶしが入るくらいの大きさです。
一方タヌキの巣穴は、バレーボールがすっぽり入ってしまうほどの大きさがあります。
イタチとタヌキでは、巣穴の周りの様子も全く違います。
イタチの場合は単独で巣作りをするため、穴は1つだけ。
周りには獲物の骨や毛が散らばっているのが特徴です。
一方タヌキは群れで生活するため、同じような大きさの穴がいくつも見られます。
- イタチの巣穴:握りこぶしサイズで骨や毛が散らばっている
- タヌキの巣穴:バレーボールサイズで複数の穴が点在している
- イタチは単独、タヌキは群れで生活する
- イタチの穴は掘り出した土が少なく、タヌキは土の山ができる
イタチvsネズミの巣穴「形状と周辺の特徴」
イタチの巣穴は完璧な円形なのに対し、ネズミの巣穴は不規則な形をしています。この形の違いで簡単に見分けることができます。
巣穴の周りの様子を見ると、さらに違いがはっきりします。
イタチの巣穴の周りには獲物の骨や毛、黒っぽい糞が散らばっているのが特徴。
一方、ネズミの巣穴の周りにはかじられた木の実や植物の食べかすが目立ちます。
「ネズミの巣かと思ったら、実はイタチの巣だった」というケースもよくあるんです。
見分け方のポイントをまとめてみましょう。
- イタチは完璧な円形、ネズミは不規則な形
- イタチは獲物の残骸、ネズミは植物の食べかす
- イタチの穴は整然と掘られ、ネズミは荒く掘られている
- イタチは1つの穴を長期使用、ネズミは頻繁に巣を移動
イタチとテンの巣穴「作られる高さ」の比較
イタチは地上3メートル以内に巣を作るのに対し、テンは5メートル以上の高所に巣を作ります。この高さの違いが、最も分かりやすい見分け方です。
「高いところにあるから絶対テンの巣だ!」とよく言われますが、実はそれだけではありません。
イタチとテンでは、巣の作り方にも大きな違いがあるんです。
イタチは地面に向かって横から掘り進めるのに対し、テンは樹洞や建物の隙間をそのまま利用する傾向があります。
見分け方のポイントを詳しく見ていきましょう。
- イタチは低め(3メートル以内)、テンは高め(5メートル以上)
- イタチは自分で掘る、テンは既存の空間を利用
- イタチは地面に近い場所、テンは木のうろや建物の隙間
- イタチの巣は泥だらけ、テンの巣は比較的きれい
イタチの巣穴に対する5つの効果的な対策

- 砂を撒いて「足跡チェック」で活動時間を把握!
- 竹ぼうきを使った「行動パターン」の確認方法
- 新聞紙で「移動ルート」を特定する裏ワザ
- 空き缶設置で「夜間の出入り」を監視する方法
- ペットボトル風車で巣穴からの「一時的な離れ」を促進
砂を撒いて「足跡チェック」で活動時間を把握!
砂を使ってイタチの足跡を調べれば、出入りの時間帯がはっきり分かります。「いつ活動しているの?」という疑問が一気に解決できる、とても役立つ方法なんです。
砂を撒く範囲は巣穴の入り口から半径30センチほど。
細かい砂なら、イタチの小さな足跡もくっきりと残ります。
「まるで動物園の足跡コーナーみたい!」と思うほど、はっきりと確認できますよ。
砂を使う時のポイントは3つあります。
- 砂は厚さ1センチ程度に均一に撒くこと
- 雨で流されないよう、天気予報をチェックしてから設置すること
- 2日に1回は新しい砂に交換して、足跡を見やすい状態に保つこと
これは他の小動物とは違う、イタチならではの特徴。
足跡の付き方を見れば、巣穴に向かう方向も分かりますし、餌を運んでいるときは足跡の間隔が広がるので、生活パターンまで把握できちゃうんです。
竹ぼうきを使った「行動パターン」の確認方法
竹ぼうきを巣穴の入り口に立てかけるだけで、イタチの出入りが一目で分かります。「まるで見張り番をつけたみたい!」と思うほど、シンプルで効果的な方法なんです。
竹ぼうきの使い方は、とってもカンタン。
- 長さ1メートルほどの竹ぼうきを用意する
- 巣穴の入り口に斜め45度の角度で立てかける
- 竹ぼうきの位置を朝と夕方に確認する
この変化を見れば、イタチがいつ活動しているのか分かるというわけ。
ただし、この方法には注意点もあります。
風の強い日は竹ぼうきが勝手に動いてしまうので、風の穏やかな日を選んで観察しましょう。
また、竹ぼうきが濡れると重くなって動きにくくなるので、雨の日は一時的に片付けるのがおすすめです。
新聞紙で「移動ルート」を特定する裏ワザ
新聞紙を使えば、イタチの移動ルートが一目瞭然。「どの道を通っているんだろう?」という謎が、手軽に解き明かせます。
新聞紙の設置方法は、とってもカンタン。
- 新聞紙を4枚重ねにして地面に敷く
- 巣穴の周りに扇状に広げて配置する
- 石で四隅を固定して風で飛ばないようにする
まるで地図に道筋を書き込んでいるみたい。
「あ、こっちの方向に行くんだ!」と、イタチの行動範囲が手に取るように分かるんです。
ただし新聞紙は、雨に弱いのが難点。
「せっかく設置したのに〜」とならないよう、天気予報をしっかりチェックしましょう。
また、朝露で濡れることもあるので、夕方に設置して翌朝確認するのがいいですよ。
破れた跡を見つけたら、赤いペンで印をつけていくと、日々の移動ルートの変化も分かります。
空き缶設置で「夜間の出入り」を監視する方法
空き缶を使えば、夜の活動を音で把握できます。「こっそり動き回るイタチの行動」が、耳で分かる優れものなんです。
空き缶の設置方法は以下の3つがポイント。
- 中身を完全に洗い流した空き缶を用意する
- 巣穴の入り口から30センチほど離して置く
- 缶を横向きに寝かせて配置する
夜中に「ころころ」という音が聞こえたら、それはイタチが活動を始めた合図。
まるで見張り番が「今、出てきましたよ〜」と教えてくれているような感覚です。
ただし、近所迷惑にならないように気をつけましょう。
缶の下に古布を敷いて音を和らげたり、缶の中に小石を入れて「からんころん」という優しい音に変えたりするのも、一つの工夫です。
ペットボトル風車で巣穴からの「一時的な離れ」を促進
ペットボトルで作った風車を設置すると、イタチを巣穴から遠ざけることができます。「カラカラ」と回る音と動きで、イタチは「ここは危険かも」と警戒するんです。
風車の作り方は思いのほかカンタン。
- ペットボトルを横半分に切って羽根を作る
- 竹ひごを支柱として差し込む
- 巣穴の近くに3本程度立てる
「何だか怖いところだな」と感じて、自然と遠ざかってくれます。
風の強い日なら、「からからから」という音も加わって効果は倍増。
ただし、この方法は2週間程度で慣れられてしまう可能性があります。
そこで、風車の位置を少しずつ変えたり、羽根の形を変えたりして、イタチを油断させないようにするのがコツ。
「今日はどんな風車かな?」とイタチを困らせることで、より長く効果を持続させられるんです。
イタチの巣穴対策での重要な注意点

- 4月から6月は「子育て期間」で特に要注意!
- 巣穴周辺1メートルは「マーキング」の危険ゾーン
- 複数の巣穴発見時は「メインの特定」が最優先
4月から6月は「子育て期間」で特に要注意!
イタチの子育て期間は、対策を誤ると思わぬ事態を招きかねません。「子イタチがいるかもしれないのに、どうしたらいいの…」と悩む方も多いはず。
この時期のイタチは特に警戒心が強く、危険を感じると子育て用の巣を放棄して別の場所に移動することがあります。
- 巣の周辺で母イタチの様子を2日程度観察してから対策を始める
- 巣の出入り口に新しい足跡がないか朝夕2回確認する
- 巣の放棄を避けるため、急激な環境変化は与えないようにする
- 子イタチの鳴き声が聞こえたら、すぐに作業を中止する
巣穴周辺1メートルは「マーキング」の危険ゾーン
巣穴の周囲1メートルには、イタチの縄張りを示す特有の臭い成分が染み込んでいます。「何だか変な臭いがするなぁ」と感じたら要注意。
この場所に近づくと、母イタチが警戒して攻撃的になることも。
- 臭い液が手や服に付着すると、なかなか取れません
- マーキングされた場所には他のイタチも寄ってくる可能性大
- 臭いが強い場所ほど、巣の中心に近い目印になります
- 雨の日は特に注意が必要で、臭いが地面に染み込んで広がることも
複数の巣穴発見時は「メインの特定」が最優先
巣穴が複数見つかった場合は、まずメインとなる巣を見極めることが大切です。イタチは「ここが安全じゃなくなってきたな」と感じると、あらかじめ作っておいた予備の巣に素早く移動します。
- 足跡や糞の量が多い巣がメインの可能性大
- 巣の周りに獲物の残骸が散らばっている場所を重点的に調査
- 朝夕の出入りが頻繁な巣がメインと判断できます
- 予備の巣はメインから30メートル以内にあることが多いんです