イタチの穴掘り被害が心配【直径10センチの穴を作る】地盤沈下や建物被害の可能性も

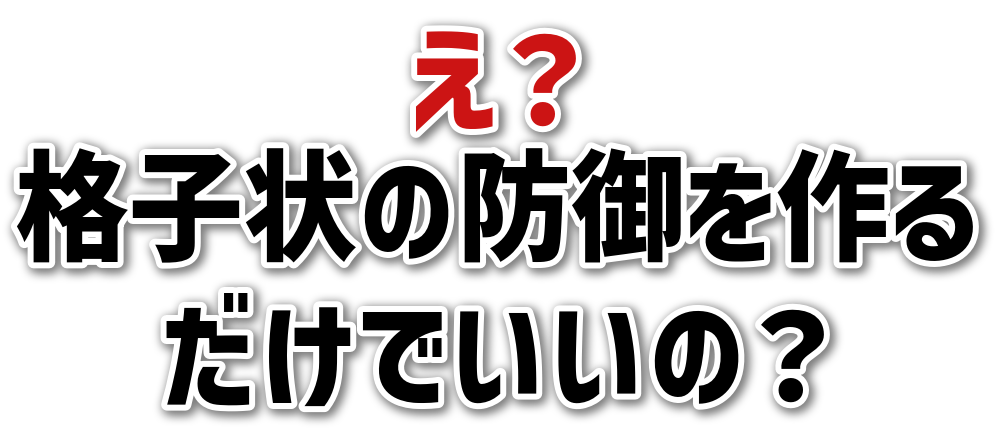
【疑問】
イタチの穴掘り被害から家を守るために最も効果的な対策は?
【結論】
建物の基礎周辺に竹串を15センチ間隔で格子状に設置することです。
ただし、設置前に子イタチがいないか確認し、穴の周囲5メートル圏内を重点的に防御する必要があります。
イタチの穴掘り被害から家を守るために最も効果的な対策は?
【結論】
建物の基礎周辺に竹串を15センチ間隔で格子状に設置することです。
ただし、設置前に子イタチがいないか確認し、穴の周囲5メートル圏内を重点的に防御する必要があります。
【この記事に書かれてあること】
庭に見慣れない穴を発見して「もしかしてイタチ?」と気になっていませんか。- 直径10センチの穴はイタチの巣作り開始のサイン
- 建物の基礎近くや南向きの日当たりの良い場所が狙われやすい
- 放置すると3ヶ月で庭全体に被害が拡大
- 竹串や金網などによる物理的な防御が最も効果的
- 対策時は子イタチの有無を必ず確認
イタチの穴掘り被害は、放っておくとわずか3ヶ月で庭全体に広がってしまう厄介な問題なんです。
直径10センチの小さな穴から始まり、知らない間に地盤を揺るがす事態に発展することも。
でも大丈夫。
穴の特徴を知って、適切な対策を取れば被害の拡大を未然に防ぐことができます。
イタチの穴掘り被害から庭を守る方法を、詳しく解説していきましょう。
【もくじ】
イタチの穴掘り被害の特徴と発生原因

- 直径10センチの穴から始まる「侵入被害」に注目!
- 斜めに掘り進められる穴が「巣作りの証」
- 水はけの良い場所に掘られる「危険な穴」に要注意
直径10センチの穴から始まる「侵入被害」に注目!
地面に空いた直径10センチの丸い穴。これがイタチの穴掘り被害の始まりです。
「ただの穴かと思ったのに…」と油断していると、わずか2週間で被害が広がってしまいます。
イタチの穴掘りには、はっきりとした特徴があります。
まず目を引くのが、穴の周りにぽろぽろと散らばった土です。
「まるで放射状に土を飛ばしているみたい」と思うほど、特徴的な形で広がっています。
掘られた穴の形状も見逃せません。
- 穴の入り口はきれいな円形で直径10センチ
- 深さは15センチほどで底が見えない
- 穴の周囲には独特の臭いが残る
「こんなに早く掘れるの?」と驚くほど、一晩で3〜5個の穴を次々と掘り進めていきます。
これは、イタチが鋭い爪と本能的な掘削能力を持っているためなのです。
斜めに掘り進められる穴が「巣作りの証」
イタチの穴には決まった掘り方があります。最初は垂直に掘り始めますが、途中から斜めに方向を変えて掘り進めていくのです。
「なぜ曲がった穴を掘るの?」その理由は、巣作りの本能にあります。
穴の構造を詳しく見ていきましょう。
- 入り口から30センチほどは垂直に掘る
- その後45度の角度で斜めに曲がる
- 最後は横方向に広がって巣を作る
まず、雨水が巣の中に流れ込むのを防ぎます。
さらに、天敵から身を守りやすい構造になっているのです。
「掘り方一つとっても、しっかり考えているんだな」と感心してしまいます。
地中の様子を観察すると、掘られた土がごろごろと表面に出てくるのも特徴です。
これは巣を広げる作業の証拠。
放っておくと、どんどん巣が大きくなっていってしまいます。
水はけの良い場所に掘られる「危険な穴」に要注意
イタチは水はけの良い場所を狙って穴を掘ります。「なぜそんな場所を選ぶの?」それは、巣が水浸しになるのを避けるためです。
特に要注意なのが、次のような場所です。
- わずかな傾斜のある地面
- 土がさらさらした乾燥エリア
- 日当たりが良く水はけの良い場所
「うちの庭、この条件に当てはまるかも…」と思った方は要注意です。
穴の周りをよく見ると、土の性質も関係していることがわかります。
やわらかすぎず、かといって固すぎない土壌を本能的に見分けて、穴を掘り始めるのです。
このような場所は、イタチにとって理想的な住処となってしまうのです。
穴掘り被害が起きやすい場所と時期

- 建物の基礎周りは「穴掘りの定番スポット」
- 日当たりの良い南向き斜面が狙われる傾向
- 地面から30センチ以内の「低い位置」に集中
建物の基礎周りは「穴掘りの定番スポット」
建物の基礎周辺は、イタチの穴掘り被害が最も多い場所です。基礎の近くは土が柔らかく、掘りやすい環境が整っているんです。
特に建物の角から50センチ以内の場所に注目が必要です。
- 基礎周りの土は建物工事の際に掘り返されているため、イタチが穴を掘りやすい柔らかさ
- 建物の基礎と地面の間に小さな隙間ができやすく、イタチが身を隠せる場所に
- 雨樋からの水で土が湿っぽくなり、穴掘りがしやすい状態に
- 基礎付近は虫や小動物が多く集まるため、イタチの餌場として認識される
日当たりの良い南向き斜面が狙われる傾向
イタチは穴掘りの場所として、日当たりの良い南向きの斜面を好んで選びます。朝日が当たって土が温かくなる場所が、イタチにとって居心地の良い環境なんです。
- 南向きの斜面は日光で土が乾きやすく、穴が崩れにくい
- 温かい土は虫や小動物が集まりやすく、イタチの餌場として最適
- 朝日で体を温められる場所は、イタチの休憩ポイントとしても重宝される
- 斜面は水はけが良く、巣穴が水浸しになる心配が少ない
地面から30センチ以内の「低い位置」に集中
イタチの穴掘りは、地面から高さ30センチ以内の低い位置に集中します。この高さは、イタチが身を隠しながら素早く出入りできる絶妙な位置なのです。
- 地面に近い位置は土が安定していて、穴が崩れにくい構造に
- 低い位置は周囲の草や植物で穴の入り口が隠れやすい
- この高さだと、イタチが飛び込むときにちょうど良い角度になる
- 地面からの湿り気が程よく保たれ、穴の形が長持ちする
穴掘り被害の状況別の比較

- 春の繁殖期vs秋の冬支度!穴掘りの頻度差
- 晴れの日vs雨の日!穴の深さ15センチと25センチ
- 朝方vs夜間!穴の直径7センチと15センチ
春の繁殖期vs秋の冬支度!穴掘り頻度差
イタチの穴掘り被害は、春と秋で大きく異なる特徴を見せます。春の繁殖期には1週間で最大10個もの穴を掘る一方、秋の冬支度の時期は2週間で3個程度にとどまります。
「なぜ春にこんなにたくさん穴を掘るの?」という疑問を持つ方も多いはず。
実は春は子育ての準備期間なんです。
巣穴を複数用意して「ここなら安全そう」「ここは日当たりが良さそう」と、まるで新築マンション選びのように慎重に場所を選んでいるのです。
一方、秋の穴掘りには別の目的があります。
- 寒さをしのぐための避難場所作り
- 冬眠に備えた食料の保管場所確保
- 寒風を避けるための待避所設置
春は「がりがりっ」と勢いよく掘り進めるのに対し、秋は「そーっと」丁寧に掘り進めます。
これは春が「とにかく数を確保したい」時期なのに対し、秋は「じっくり良い巣を作りたい」時期だからなのです。
まさに「速さと丁寧さの違い」というわけです。
晴れの日vs雨の日!穴の深さ15センチと25センチ
天候によってイタチの穴掘り方は大きく変化します。晴れの日は深さ15センチ程度の浅めの穴なのに対し、雨の日は最大25センチまでの深い穴を掘ります。
「どうして雨の日のほうが深いの?」という声が聞こえてきそうです。
これには理由があるんです。
雨で柔らかくなった土は掘りやすく、さらに水はけを考えて深めに掘る必要があるからです。
穴の形状にも特徴的な違いが見られます。
- 晴れの日:真っすぐな縦穴型
- 雨の日:斜めに曲がった排水型
- 雨上がりの日:階段状の段差型
晴れの日は「さくさく」と素早く掘り進められますが、雨の日は「じとじと」した土に気を配りながら、慎重に穴を掘り進めていくのです。
朝方vs夜間!穴の直径7センチと15センチ
1日の時間帯によって、イタチの穴掘りパターンは驚くほど変化します。朝方は直径7センチの小さな穴を掘るのに対し、夜間は直径15センチの大きな穴を掘ります。
これには理由があるんです。
朝方は周囲の目が気になり、さっと掘って「すばやく逃げ場所を確保したい」という心理が働きます。
一方、夜間は「ゆっくり掘れる」という安心感から、より大きな穴を作るのです。
時間帯による穴の特徴をまとめると:
- 朝方:浅くて小さな避難用の穴
- 日中:ほとんど穴掘りはしない
- 夕方:中型の探索用の穴
- 夜間:大きな巣作り用の穴
朝方は「さっさっ」と急いで掘るのに対し、夜間は「ごりごり」とじっくり掘る傾向があるのです。
まるで工事現場の作業時間帯による騒音への配慮のようです。
5つの穴掘り被害への予防策
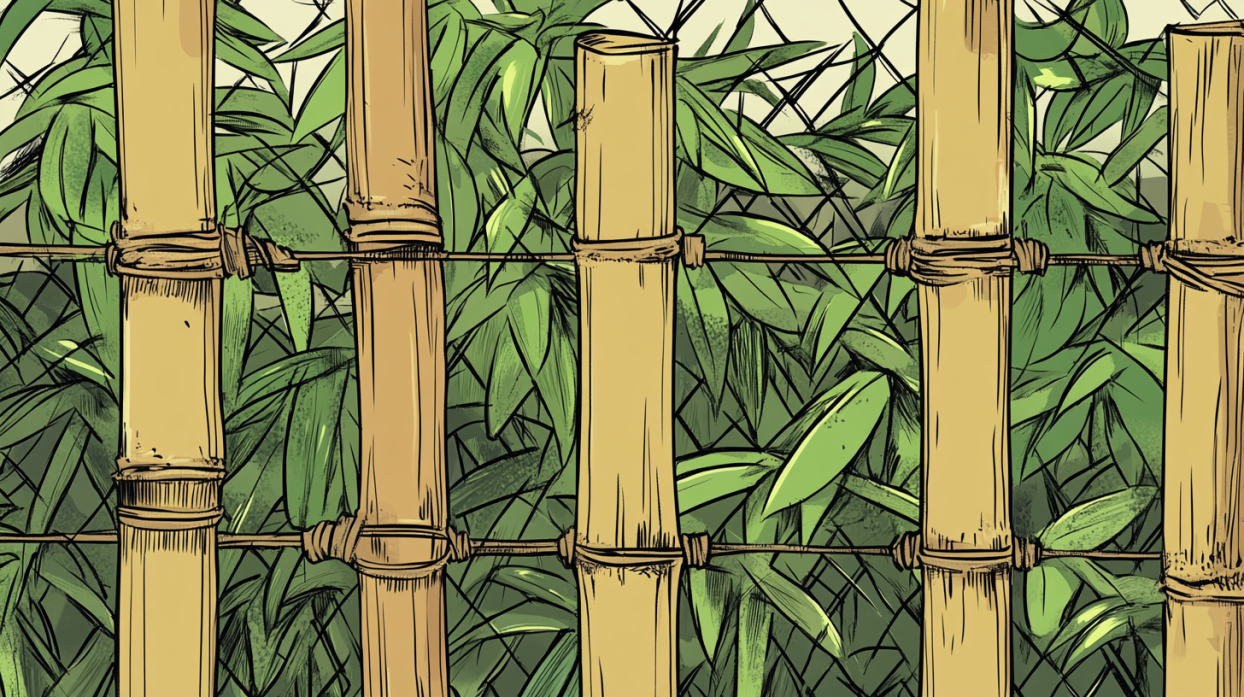
- 竹串による「格子状の防御壁」で穴掘りを阻止
- 砂利と土を混ぜた「硬い地面」で対策
- トゲのある植物で「進入ルート」を遮断
- 金網の敷設で「完全防御」を実現
- 振動式の杭で「警戒地帯」を形成
竹串による「格子状の防御壁」で穴掘りを阻止
竹串を使った格子状の防御壁を作ることで、イタチの穴掘り被害を効果的に防ぐことができます。長さ30センチの竹串を地面に規則正しく刺していくだけの簡単な対策です。
「こんな単純な方法で本当に効果があるの?」と思われるかもしれませんが、びっくりするほどの効果を発揮します。
竹串の配置方法がとても大切です。
間隔を15センチにして、がっちりと格子状に組んでいきましょう。
竹串は地面に深く刺すのがコツで、全体の3分の2まで土に埋まるようにします。
こうすることで、ぐらつきもなくしっかりと防御壁として機能するんです。
- 竹串は長さ30センチのものを選ぶ
- 間隔は15センチの格子状に配置する
- 地面には竹串の3分の2まで刺す
すると、イタチは「うーん、ここは掘れそうにないぞ」とばかりに、すぐに別の場所へ移動していってしまうのです。
竹串は雨に濡れても腐りにくく、3ヶ月は交換なしで使えます。
ただし、竹串が抜けかかっていないかどうか、週に1回はぱらぱらと見回って確認することをお勧めします。
砂利と土を混ぜた「硬い地面」で対策
砂利と土を混ぜ合わせて地面を固めることで、イタチが穴を掘れないように工夫できます。砂利は直径2センチ程度のものを選びましょう。
大きすぎても小さすぎても効果が薄れてしまいます。
「どのくらいの量を混ぜればいいの?」という疑問に対しては、土と砂利の割合を2対1にするのがおすすめです。
混ぜ合わせる際は、がっしりと固まるように深さ20センチまで均一に混ぜ込みます。
すると、イタチが「この地面は固くて掘れないな」とあきらめるほどの硬さになります。
- 直径2センチの砂利を使用
- 土と砂利の割合は2対1の配合
- 深さ20センチまで丁寧に混ぜ込む
ごりごりと爪を立てても、ぱらぱらと砂利が邪魔をして穴を広げられないのです。
ただし、水はけの良さは保つ必要があります。
砂利を混ぜすぎると水たまりができやすくなってしまうので、2週間ほど様子を見て調整することをお勧めします。
トゲのある植物で「進入ルート」を遮断
トゲのある植物を戦略的に配置することで、イタチの侵入経路を効果的に遮断できます。バラやさんざしなどのとげとげした植物を、地面から30センチの高さで刈り込んで生垣のように育てます。
「刺があるだけで本当に効果があるの?」と思われるかもしれませんが、イタチは柔らかな毛皮を大切にする習性があり、とげのある場所は本能的に避けるんです。
植物の配置方法がとても重要です。
間隔を50センチ以下にして、すき間なく植えていきましょう。
- 地面から30センチの高さを保つ
- 植物の間隔は50センチ以下に設定
- 刈り込みは3ヶ月に1回行う
イタチは「ちくちくして痛そうだな」とばかりに、さっと別のルートを探しに行ってしまうのです。
とげのある植物は見た目も良く、お庭の景観を損なうことなく対策できる利点があります。
ただし、植物の成長に合わせて定期的な刈り込みが必要です。
草むらになってしまうと、イタチの隠れ家になってしまう危険性もあるので注意しましょう。
金網の敷設で「完全防御」を実現
地面に金網を敷き詰めることで、イタチの穴掘りを物理的に阻止できます。網目1センチの金網を選び、地面にぴったりと敷き詰めていきます。
「見た目が悪くならないかしら」という心配もあるでしょうが、土で覆えば目立たなくなります。
金網の上には5センチの厚さで土をかぶせましょう。
これが重要なポイントです。
- 網目1センチの金網を使用
- 土による覆土を5センチ確保
- 金網の継ぎ目は10センチ以上重ねる
イタチは「どこを掘っても金網に当たってしまう」とばかりに、すぐにあきらめて立ち去ってしまいます。
ただし、金網が地面から露出したり、継ぎ目が開いたりしていないか、月に1回は見回りが必要です。
また、庭木の根が金網に絡まないよう、植物の周りは15センチほど空けておくことをお勧めします。
振動式の杭で「警戒地帯」を形成
振動式の園芸用杭を利用することで、イタチを寄せ付けない警戒地帯を作り出せます。地面から10センチほど突き出すように杭を設置します。
振動で地面がびりびりと震えることで、イタチは「この場所は危険だぞ」と感じ取り、近づかなくなるんです。
設置する間隔が効果を左右します。
3メートルごとに1本の杭を配置していきましょう。
- 地面からの突出は10センチに調整
- 間隔は3メートルごとに設置
- 動作確認は週に2回実施
地面をぶるぶると震わせることで、「この場所は安全じゃないな」という警戒心を与えるのです。
ただし、雨天時は感電の危険があるため、必ず電源を切っておきましょう。
また、振動が弱くなってきたら電池の交換時期です。
月に1回は電池残量も確認することをお勧めします。
イタチの穴掘り対策時の重要な注意点

- 子イタチがいないか「事前確認」が不可欠!
- 穴を急いで埋めるのは「逆効果」の危険性
- 強い臭いの薬剤は「マーキング誘発」に注意
子イタチがいないか「事前確認」が不可欠!
巣穴に子イタチがいる場合は、慎重な対応が必要です。まずは子イタチの有無をしっかりと確認しましょう。
「早く穴をふさぎたい気持ちはわかるけど…」と焦る気持ちをぐっとこらえて、子イタチがいないかどうかをじっくり観察することが大切です。
特に春と秋は繁殖期なので要注意。
穴の周りに次のような特徴がないか、確認してみましょう。
- 穴の周りに小さな足跡がたくさんついている
- キーキーという鳴き声が聞こえる
- 夕方になると小さな影がちらちら動く
- 餌の食べかすが散らばっている
穴を急いで埋めるのは「逆効果」の危険性
見つけた穴をすぐに土で埋めてしまうのは、実は大きな間違いです。むしろイタチの穴掘り行動を活発化させてしまう危険性があります。
「とにかく早く穴をなくしたい!」という気持ちはよくわかります。
でも、ちょっと待ってください。
穴を急いで埋めると、どうなるでしょう。
イタチは「せっかく掘った巣が壊された!」と考えて、より一層熱心に穴を掘り始めちゃうんです。
- 新しい穴が次々と増える
- 掘る深さが倍になる
- 周辺地域まで被害が広がる
強い臭いの薬剤は「マーキング誘発」に注意
強い臭いの薬剤を使って追い払おうとするのは、かえって事態を悪化させてしまいます。イタチの習性を知らないと、とんでもないことになっちゃうんです。
「強い薬剤で一気に追い払おう!」という考えは、実はイタチの習性を逆なでしてしまいます。
なぜなら、イタチは強い臭いに反応して、自分の臭い付けを始めてしまうからです。
- マーキング行動が活発になる
- より広範囲に臭いを付ける
- 他のイタチまで集まってくる
- 被害が倍増する可能性がある