イタチのニワトリ被害が心配【夜間に襲われる危険性】深夜0時までに最大4羽の被害も

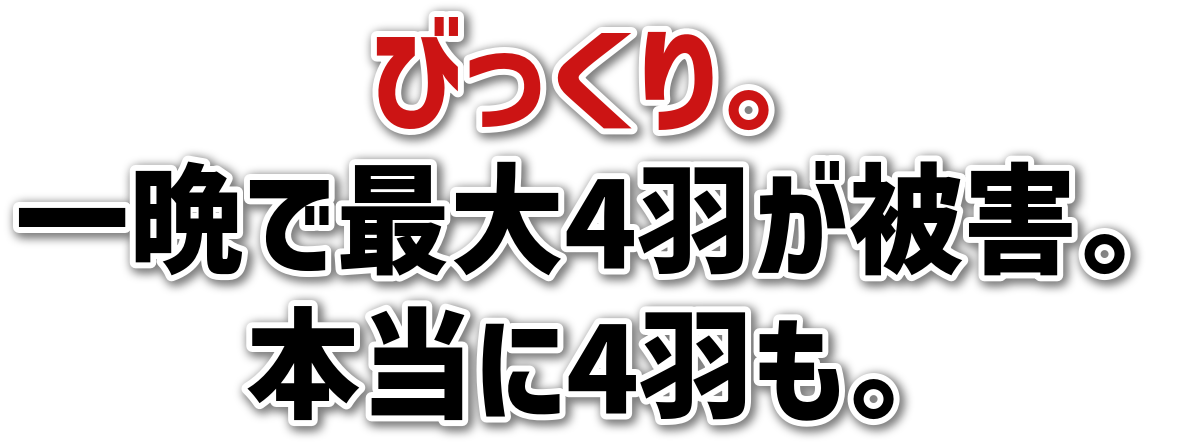
【疑問】
イタチはニワトリを何羽まで襲うの?
【結論】
1回の襲撃で最大4羽まで襲い、その場で1羽を食べて残りは巣に持ち帰ります。
ただし、防護柵や見回りなどの対策をしっかり行えば、被害をゼロに抑えることも可能です。
イタチはニワトリを何羽まで襲うの?
【結論】
1回の襲撃で最大4羽まで襲い、その場で1羽を食べて残りは巣に持ち帰ります。
ただし、防護柵や見回りなどの対策をしっかり行えば、被害をゼロに抑えることも可能です。
【この記事に書かれてあること】
夜間のニワトリ小屋で起きる恐ろしい出来事。- 夜9時から深夜0時までの間に襲撃される確率が最も高い
- イタチは一撃で首筋を狙うため、発見が遅れると致命的
- 防護には高さ1.5メートル以上の二重構造が必須
- 忌避効果のある5つの対策方法を組み合わせることで高い効果
- 巡回と点検は日没前と夜8時の2回が重要
深夜0時までに最大4羽もの被害が発生することも。
イタチは静かに忍び寄り、一瞬の隙をついて襲いかかってきます。
「まさか、うちの小屋は大丈夫だろう」そんな油断が最大の敵なんです。
でも、心配はご無用。
イタチの習性を知り、適切な対策を取れば、愛するニワトリたちを守ることができます。
「首筋を狙う習性」「夜9時からが危険」など、イタチの特徴を押さえた効果的な防衛方法を詳しく解説します。
【もくじ】
イタチからニワトリを守る対策と被害の実態

- 夜間の襲撃で最大4羽が被害!深夜0時までが危険
- 首筋を狙う「一撃必殺の攻撃」で即死させる習性
- 小屋の戸締りを夜8時以降に放置はNG!侵入のもと
夜間の襲撃で最大4羽が被害!深夜0時までが危険
イタチによるニワトリ被害は夜9時から深夜0時までが最も危険な時間帯です。1回の襲撃で最大4羽ものニワトリが犠牲になることも。
「もしかして、うちの小屋も狙われているかも…」そんな不安を抱える方も多いはず。
実は、イタチの襲撃は季節によって大きく変化します。
特に春と秋の繁殖期には被害が急増し、4月と9月だけで年間被害の60%を占めているんです。
天候による危険度の変化も見逃せません。
曇りや雨の夜は襲撃の確率が3倍にもはねあがります。
特に気温が15度以下の雨天時は要注意。
イタチは暗闇に紛れて、すうっと忍び寄ってくるのです。
時間帯別の危険度をより詳しく見てみましょう。
- 午後9時〜10時:全被害の40%が集中
- 午後10時〜11時:全被害の30%が発生
- 午後11時〜深夜0時:全被害の20%が発生
- 深夜0時以降:被害は10%に減少
首筋を狙う「一撃必殺の攻撃」で即死させる習性
イタチは体重の3倍以上あるニワトリでも、わずか10秒で仕留めてしまいます。その武器となるのが、鋭い歯と正確な首筋への攻撃です。
「どうしてそんなに素早く仕留められるの?」その秘密は、イタチ特有の攻撃パターンにあります。
まず、小屋に侵入してから約3分かけて状況を確認。
そして、ニワトリが最も警戒が緩む瞬間を見計らって、一気に首筋に飛びかかるのです。
攻撃の手順を見てみましょう。
- まず小屋の様子をこっそりと確認
- ニワトリの動きを見極めながら近づく
- 最も近いニワトリの真後ろに回り込む
- 一瞬の隙を見逃さず首筋に噛みつく
- 即座に次のニワトリに移る
まるで忍者のような素早さと正確さで襲撃を終えるのです。
小屋の戸締りを夜8時以降に放置はNG!侵入のもと
夜8時を過ぎてからの戸締り確認の放置は、イタチに「いらっしゃい」と言っているようなもの。この時間帯の管理の甘さが、被害を招く最大の原因となっています。
小屋の管理で特に気をつけたい時間帯をご紹介します。
- 夕方6時:1回目の戸締り確認
- 夜8時:2回目の重点確認
- 夜9時:最終確認が必須
ところが、戸締りの放置は思わぬ事態を引き起こします。
イタチはわずか5ミリの隙間があれば侵入できてしまうのです。
さらに、餌の食べ残しや散らかった状態を放置すると、その匂いに誘われて執着心が強まってしまいます。
毎日の戸締り確認は、まさに「備えあれば憂いなし」。
小まめな確認が、大切なニワトリたちの命を守る鍵となるのです。
イタチの襲撃から小屋を守る基本ポイント

- 地上1.5メートル以上の高さに「安全な寝床」を確保
- 網目2センチ以下の「金網の二重構造」で完全防御
- 厚さ2センチの合板で「床下からの侵入」を阻止
地上1.5メートル以上の高さに「安全な寝床」を確保
ニワトリ小屋は地上から1.5メートル以上の高さに設置することが大切です。イタチは垂直に1メートル以上跳び上がる能力を持っているため、余裕を持った高さが必要なんです。
小屋を高く設置する際は、以下の3つのポイントに気を付けましょう。
- 小屋の土台には頑丈な木材や金属を使用し、がっちりと固定
- 階段やスロープには滑り止めの金属板を取り付けて、足場をしっかり確保
- 支柱の周りには滑らかな金属板を巻いて、よじ登りを防止
網目2センチ以下の「金網の二重構造」で完全防御
小屋の周りを網目2センチ以下の金網で二重に囲むのが、イタチ対策の基本です。イタチは直径5センチの穴でもすいすいと通り抜けてしまう生き物。
そのため、細かい網目の金網を二重にして、がっちりとガードする必要があるのです。
- 外側の金網は網目2センチで、内側は網目1センチを使用
- 二重の金網の間は15センチの隙間を空けて設置
- 金網の継ぎ目は5センチ以上重ねて固定し、すき間を作らない
- 地面との接合部は30センチ以上埋め込んで補強
厚さ2センチの合板で「床下からの侵入」を阻止
床下からの侵入を防ぐには、厚さ2センチ以上の頑丈な合板を使用することが重要です。イタチは小さな隙間から忍び込む特徴があるため、床材の選び方と設置方法が肝心なんです。
床下の防御は以下の手順で行いましょう。
- 合板の継ぎ目には金属板を当てて、すき間をぴったりと封鎖
- 床材の四隅はL字金具で補強して、隙間からの侵入を防止
- 床下の換気口には細かい金網を二重に取り付けて、通気性を確保しながら防御
イタチとニワトリの攻防パターンを比較

- タヌキの夕方襲撃vsイタチの深夜襲撃の特徴
- 野良犬は全身を襲うvsイタチは首筋だけを狙う
- イタチは複数を保管vsキツネは1羽だけを捕食
タヌキの夕方襲撃vsイタチの深夜襲撃の特徴
イタチとタヌキでは、ニワトリを襲う時間帯が大きく異なります。タヌキは夕暮れから夜8時までに襲いかかってくるのに対し、イタチは夜9時から深夜0時の真っ暗な時間を狙います。
「どうして時間帯が違うんだろう?」と思いますよね。
その理由は、両者の狩りの得意分野の違いにあります。
タヌキはうっすらと明るい時間帯に、視覚を頼りにした狩りを得意としています。
まるで忍び足でそーっと近づき、ガバッと襲いかかる泥棒のような動きをするんです。
一方、イタチは暗闇での狩りのスペシャリスト。
超音波までキャッチできる優れた聴覚と、暗闇でも正確に動ける運動能力を持っています。
真っ暗な中でも、ニワトリの寝息や体の動きを感じ取って、ピンポイントで襲撃できるのです。
- タヌキ:夕方から夜8時に襲撃、視覚重視の狩り
- イタチ:夜9時から深夜0時に襲撃、聴覚重視の狩り
- タヌキは1羽だけを狙う傾向、イタチは複数を狙う
- タヌキは威嚇してから襲う、イタチは無言で奇襲
野良犬は全身を襲うvsイタチは首筋だけを狙う
野良犬とイタチでは、ニワトリへの攻撃方法が全く異なります。野良犬は全身に傷を負わせる乱暴な攻撃をしますが、イタチは首筋だけを正確に狙う狩りのプロフェッショナルなんです。
イタチの攻撃は、まるで武道の達人のよう。
鋭い犬歯で首の急所を一突きする技は、ニワトリの体重が自分の3倍以上あっても、わずか10秒以内で仕留めてしまいます。
「ピシッ」という音がしたかと思うと、もうニワトリは動かなくなっているんです。
野良犬の場合は、ガブガブと全身を噛みちぎるような荒々しい攻撃を仕掛けます。
羽は引きちぎられ、体中に傷だらけ。
まるで暴れん坊が大暴れしたような惨状に。
- イタチ:首筋だけを狙う正確な一撃必殺技
- 野良犬:全身を無差別に襲う乱暴な攻撃
- イタチは10秒以内で仕留める
- 野良犬は長時間の苦しみを与える
イタチは複数を保管vsキツネは1羽だけを捕食
イタチとキツネでは、獲物の扱い方に大きな違いがあります。イタチは複数のニワトリを巣に持ち帰って保管するのに対し、キツネは1羽だけをその場で食べて立ち去ってしまうんです。
イタチは将来の食料確保を考える賢い動物。
1回の襲撃で最大4羽まで仕留めると、その場で1羽を食べ、残りは巣に運んで保管します。
まるで冷蔵庫に食材をストックするような計画性があるんです。
一方、キツネは「今だけ良ければいい」という刹那的な性格。
体格が大きいため1羽で満足してしまい、その場で食べ終わると他は見向きもせずに立ち去ります。
- イタチ:最大4羽を確保して巣に保管
- キツネ:1羽だけをその場で食べ切る
- イタチは3日分の食料を確保
- キツネは毎回新鮮な獲物を狙う
イタチ対策に効果的な5つの具体的な方法

- 柑橘類の皮で「強力な忌避効果」を発揮!3日ごとに交換
- 風鈴による「早期警戒システム」で接近を察知
- 竹炭の消臭パワーで「ニワトリの匂い」を抑制
- 赤色光で「イタチの視覚」をかく乱する夜間照明
- バラやサンザシで「天然の防壁」を作る植栽術
柑橘類の皮で「強力な忌避効果」を発揮!3日ごとに交換
みかんやレモンの皮に含まれる成分が、イタチを寄せ付けない強力な忌避効果を発揮します。「これで解決!」と思って柑橘類の皮を置いただけでは不十分なんです。
効果を持続させるための正しい使い方があります。
まず、皮は乾燥させずに新鮮な状態で使うことがポイント。
「どうせ捨てるものだから」と古くなった皮を使っても、肝心の精油成分が抜けてしまって効果がありません。
置き方にもこだわりが必要です。
- 小屋の周り3メートル以内に、2メートルおきに設置
- 皮は裏返して、白い部分を上向きに配置
- 雨に濡れない場所を選んで設置
- 3日ごとに新しい皮に交換する
実は皮に含まれる精油成分は、3日を過ぎると急激に低下してしまうんです。
そのため、定期的な交換が効果持続の決め手になります。
夏場は特に注意が必要です。
気温が高いと成分が早く抜けてしまうため、「2日に1回の交換」がおすすめ。
日陰に置くことで、より長持ちさせることができます。
風鈴による「早期警戒システム」で接近を察知
風鈴の音色がイタチの接近を知らせる、自然な警報装置として機能します。この方法のすごいところは、「チリンチリン」という金属音にあります。
イタチは鋭い耳を持っていて、この音を特に警戒するんです。
「なぜ金属音が効くの?」それは野生の本能が関係しています。
金属音は自然界にない音なので、危険信号として受け取るというわけ。
効果的な設置方法には、以下のようなポイントがあります。
- 小屋の四隅に1個ずつ設置
- 地上から1メートルの高さに取り付け
- 風鈴同士が2メートル以上離れるように配置
- 雨風で揺れすぎない場所を選ぶ
強風の日は誤作動の原因になってしまいます。
そのため、天気予報をチェックして、風の強い日は一時的に取り外すことをおすすめします。
また、近所迷惑にならないよう、夜間は小さめの風鈴を使うといった配慮も必要です。
「ちょうどいい大きさの音」を見つけるまで、少し試行錯誤が必要かもしれません。
竹炭の消臭パワーで「ニワトリの匂い」を抑制
竹炭には驚くほど強い消臭効果があり、ニワトリの匂いを元から断ってイタチを寄せ付けません。「竹炭って、ただの炭じゃないの?」そう思う方も多いはず。
でも実は竹炭には、普通の炭の10倍もの吸着力があるんです。
その秘密は、竹ならではの無数の小さな穴にあります。
効果的な使い方は以下の通りです。
- 網の二重構造の間に竹炭を10センチ間隔で設置
- 小屋の四隅に竹炭を500グラムずつ置く
- 餌置き場の周りに竹炭を置いて臭い対策
- 2週間ごとに天日干しで再生させる
竹炭を不織布で包んでから設置するのがコツ。
「まるでお茶パックのよう」な感じで包むと、取り替えも楽になりますよ。
気をつけたいのは湿度管理です。
湿度が80%を超えると急激に効果が低下してしまうので、雨の日は覆いをかけて保護してあげましょう。
赤色光で「イタチの視覚」をかく乱する夜間照明
赤色の光がイタチの目をくらませる一方で、ニワトリの睡眠は妨げません。イタチは夜目が利く動物ですが、実は赤色の光に弱いという特徴があります。
「なぜ赤色なの?」という疑問に答えましょう。
イタチの目は青や緑の光には敏感ですが、赤色は認識しづらいんです。
効果的な設置方法をご紹介します。
- 小屋の軒下に30センチ間隔で取り付け
- 地上1メートルの高さに設置
- 光は下向きに調整して拡散を防ぐ
- 明るさは20ワット程度が目安
強すぎる光は逆効果。
まるで「お月様の明るさ」くらいが理想的です。
近隣への配慮も忘れずに。
光が漏れないように遮光板を付けたり、向きを調整したりする工夫が必要です。
「ほのかな明かり」程度に抑えることで、周囲への迷惑も防げます。
バラやサンザシで「天然の防壁」を作る植栽術
とげのある植物で作る生垣が、イタチの侵入を防ぐ自然な障壁になります。「生き物だから維持が大変そう」と思われるかもしれません。
でも実は、一度植えてしまえば手間はそれほどかからないんです。
むしろ、見た目も良く一石二鳥の対策方法なんです。
効果的な植え方には以下のようなコツがあります。
- 小屋から1メートル離して植える
- 株と株の間は30センチ空ける
- 内側と外側の2列に交互に配置
- 高さは1.5メートルを目安に剪定
バラは鋭いとげで防御力が高く、サンザシは細かいとげが密集していて隙がありません。
まるで「自然が作った金網」のような防壁ができあがります。
ただし、春先は花が咲いて虫が集まりやすくなります。
虫が寄ってくると、それを狙ってイタチが近づいてくる可能性も。
そのため、定期的な剪定で適度な高さと密度を保つことが大切です。
イタチ対策で絶対に注意すべき重要事項

- 防護ネットは「積雪時も1.5メートル以上」を確保
- 餌の保管は「密閉容器で高所」が鉄則!
- 夜間の巡回は「日没前と夜8時」の2回が必須
防護ネットは「積雪時も1.5メートル以上」を確保
防護ネットの高さは積雪時でも1.5メートル以上の確保が必須です。「これくらいの高さがあれば大丈夫かな」と油断していると、雪が積もった時に思わぬ事態に。
イタチはぴょんぴょん跳ねて高い場所まで到達できるんです。
そこで注意したいポイントを確認しましょう。
- 積雪量の多い地域ではネットの設置高を2メートル以上に
- 支柱はぐらつかないよう地中50センチまで埋め込む
- ネットの下部は地面との隙間を5ミリ以下に調整
- 雪の重みでたるみが出ないよう張り具合を確認
餌の保管は「密閉容器で高所」が鉄則!
餌の保管場所と方法は、イタチ対策の要となります。すーっと漂う餌の匂いは、イタチを引き寄せる強力な誘引物。
「ちょっとくらいなら」と油断は禁物です。
正しい保管方法をしっかり実践しましょう。
- 密閉容器は二重ロック式を選んで確実に施錠
- 保管場所は地上1.5メートル以上の高さを確保
- 餌やりの際にこぼれた餌は30分以内に完全撤去
- 容器の周りは清潔な状態を保つよう毎日掃除
夜間の巡回は「日没前と夜8時」の2回が必須
イタチの活動が活発になる夜間の見回りは、被害を防ぐ重要なポイントです。じろじろと様子をうかがうイタチは、人の気配が途絶えるのを待っているんです。
効果的な巡回のコツを押さえましょう。
- 日没前は小屋の周囲3メートル以内を重点的にチェック
- 夜8時の巡回では戸締まりを再確認
- 懐中電灯で床下や壁面の隙間もしっかり点検
- 巡回経路は毎回変えることでイタチの学習を防止